現実を直視するには、「酔い」が必要だった。バラバラの心にアディクションは何をしてくれたか
その人にとって、依存することにどんな意味があり、何の役割を果たしていたのか。それを改めて問い直してみたい。
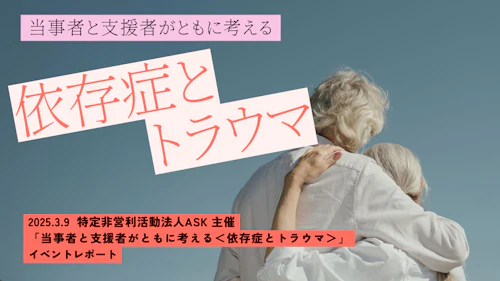
公開日:2025/03/31 06:00
本記事では、2025年3月9日に特定非営利活動法人ASK主催のもと行われたイベント、「当事者と支援者がともに考える<依存症とトラウマ>」のレポートをお届けする。
ASK認定依存症予防アドバイザーであり、依存症当事者の後藤勝さん、平出明彦さん、後藤早苗さんの3名が登壇。アナウンサーの塚本堅一さんの司会進行の下、トラウマインフォームドケアに詳しい臨床心理士の野坂祐子さん、依存症専門医の松本俊彦さんをゲストに、自身のアディクションを「トラウマ」の観点から語った。
(注)本記事ではイベントの特性上、トラウマやPTSDに関連する体験談を扱っています。事件・事故・暴力被害などの直接的な表現は極力控えていますが、読んでいる最中に気分が悪くなったり不安を感じたりする可能性があります。無理せず、体調と相談しながらの閲覧をお勧めします。
(文:遠山怜)
生き残った罪悪感と虚無。バラバラの心を繋ぎ止めたのはアルコール

現在、カメラマンとして活躍する後藤勝さん。戦場カメラマンに憧れていた後藤さんは、20代の頃、単身でコロンビアへ。1990年代のコロンビアは、肥沃な土地を巡って政府軍と右派民兵、左翼ゲリラによる三つ巴の内戦が続いていた。特に80年代に結成された右派民兵による民間人への襲撃が増えていた。
後藤さんは現地の人権擁護団体に所属し、襲撃現場の記録写真を撮っていたが、事態を隠蔽したい右派民兵に命を狙われる。16名いたチームのうち、生き残ったのは後藤さん含めて2人だけだった。コロンビアを脱出し、ニューヨークに居を構えた後藤さんだったが、ある異変が起きる。
「うしろに人が立つと、恐怖を感じるんです。戦地では急襲されないよう、いつもうしろを警戒していました。ニューヨークのような大都市にきても、その癖が抜けない」
次第に人付き合いを避けるようになり、写真家としての活動を控え、レストランでウエイターを始める。しかし、何をしていても、心のなかはいつも罪悪感で満ちていた。なぜ仲間ではなく、自分だけが生きているのか。真実のためなら命も惜しまなかったのに、今何をしているのか。引き裂かれた心を埋めたのが、アルコールだった。
「それこそ、浴びるように飲んでました。意識がある間は、ひたすらアルコールを自分の体に流し込み続けていた。自分でも何をしているのかわからないが、とにかくそうする必要があった」
「あるとき、人から専門家に診てもらった方がいいと言われて。当時、トラウマという概念はまだあまり一般的ではありませんでしたが、たまたま住んでいた地域には多くの帰還兵がいて、カウンセリングが広く行われていたんです。そこで、戦時下体験トラウマによるPTSDだと言われました」
トラウマを抱えて、再び戦場へ
90年代は、紛争の絶えない動乱の時代だった。後藤さんは、再び戦地に赴き、現場で起きていることを報じ続けた。トラウマの原因に、自ら飛び込んだのはなぜなのか。
「戦地で今まさに起きていることを伝えられるこの仕事は、とても意義があると思っていました。情報が歪められて伝播する世界では、事実はとても貴重なものだから。それに、戦禍を離れて別のことをすれば、また酒浸りの日々になるとわかっていた。だから、自分のライフワークを手放そうとは思わなかったんです」
戦争時トラウマのことは、何十年も人に話さなかったが、あるとき学生に講演してみないかと誘いを受けた。自身の体験を語る講演活動は、今も続けている。改めて、後藤さんにとって、回復とはどんなものだったのか。
「回復とは、手放すことだと言われています。過去の記憶、被害体験、失ったものへの執着から解放されること。でも、自分の場合は、手放さずに持ち続け、それを人に話すことがライフワークになっています。忘れるのではなく抱え続ける。それが自分にとっての回復のように思います」
回復には「痛み」と「恥」が伴う

臨床心理士として、当事者支援に関わる野坂祐子さんは、回復について「一般的にイメージされるものと、当事者が体験する回復にズレがある」と指摘する。
「アディクションは、当事者にとって何らかの必要性があって生じているものです。依存症は、自分を苦しめる側面と、自分を支え守ってくれるという、2つの側面がある。ですから、回復することでアディクションから解放される反面、見ないようにしていた厳しい現実に、向き合わなくてはならない。今まで感じずに済んでいた感情、忘れていた記憶が一気に押し寄せる。それはとても苦しいことです」
「回復したら、被害を受けた証拠が失われるのではと恐れる人もいます。元気を取り戻すことで、周囲や加害者から『たいしたことではなかったのだろう』と思われるかもしれない。自分に非がないにもかかわらず、『自分が悪かった』と、罪悪感を抱くことにつながる恐れもあります。回復とは、罪悪感や恥の気持ちを手放していくことを指しますが、このプロセスには痛みが伴います」
「当事者は、回復に伴うこうした傷つきを恥に思わなくていいし、ごまかさなくてもいいんです。その一方、支援者は回復を名目に、相手の痛みを勝手にコントロールしようとしていないか、注意する必要があります。回復して楽になるのは、むしろ支援者の方なんです。『自分がしてきた支援は無駄ではなかった』と安心できますから」
宗教虐待で奪われたもの

平出明彦(ネット上では、ちざわりんの名でも活動中)さんは、虐待を受けた宗教2世のひとりだ。現在は公認心理師・社会福祉士として働く傍ら、宗教2世や心の問題に関する発信もしている。平出さんは、「特定の宗教の是非を問いたいわけではない。あくまで自分の経験を話すことで、対話のきっかけとしたい」と前置きしたうえで、こう話す。
「母親はエホバの証人の信者で、子どもの頃から宗教活動に強制的に参加させられました。週3回の集会、土日の布教活動。信者以外との自由な交流は禁じられ、教えにそむくと鞭で打たれました。大学への進学や一般企業への就職は禁じられ、少しでも宗教活動から離れようとすると、『滅ぼされる』と脅されました」
転機となったのは、20歳の頃。元信者による告発本を読んだことをきっかけに、信じてきた教義の矛盾や嘘に気づいてしまう。人生のすべてをつぎ込み、ひたすら求め続けた「救い」は存在しないと知った。
「自分は、今までずっと騙されていた。青春の貴重な時間も、友人もお金も失って、自分には何も残っていない。急に現れた現実に、シラフでは向き合えなかった。誰も彼も、自分をバカにしている気がして、自宅でとにかく飲み続けていました。ギャンブルに通い、違反速度でめちゃくちゃな運転をしたり、素手でガラスを割ったりと、自己破壊的な行動がやめられなかった」
「これが自分にとっては自己治療だったんです。全部奪われて何もない自分を、壊してしまいたかった。でもその反面、まともな人間になりたい気持ちも人一倍あった」
自分を破壊したい思いと、他の人のように真っ当になりたい思い。矛盾した気持ちを抱えた平出さんは、ある日、滞在していた簡易宿泊所で酔って暴れ、警察沙汰になった。
「べろべろになりながら、『俺だってまともな人間になりたいんだよ』と叫んでいたら、駆けつけた警察官から『基本に忠実に生きれば、まともになれる』と諭されて。通報した宿主も『若いんだからやり直せる』と言ってくれて、お咎めなしにしてくれた。本当にどうしようもない自分を、受け入れてくれた人がいた」
回復とは、回復し続けること
真人間になりたい。そう決意した平出さんは、8ヶ月限定で介護職につく。すると利用者に働きぶりを褒められるようになる。自分は生きていてもいいのだと、その時思った。その後、社会福祉士として働き、子どもにも恵まれた。自分はもうすっかり回復したと思っていた平出さんだが、事態は一変する。
「そのとき、たまたま性暴力被害者支援の研修を受けていたんです。そこで、解説されていたPTSDの症状が、自分の身に起きていたのと同じだと気づいて。運悪く、絶縁していた母親から連絡があったこともあり、フラッシュバックに苦しめられるようになりました。自分はまだ回復しきっていなかったんだと、その時わかりました」
フラッシュバックの最中、支えになってくれたのはトラウマケアの知識だった。
「今起きていることは、PTSDの症状なんだとわかることで、少し冷静になれたんだと思います。あとは、安全なピアサポートの場で、自分の気持ちを吐き出すこと。これは今も続けていて、今も回復の途中で歩みを進めています」
フラッシュバックへの対応は「気づくこと」から
PTSDの症状の一つに、「侵入的回想」というものがある。特定の出来事が頭の中で繰り返しよみがえり、制御することができない状態を指す。医師の松本俊彦さんは、こうしたフラッシュバックへの対処法についてこう話す。
「まずは、今、自分の身に起きていることはフラッシュバックなんだ、と気づけることが重要です。PTSDの症状を知っておくことで、状況に対して冷静に考える余裕が生まれやすくなります。知識は、自分を守る武器にもなりますから、症状がひどくないときにネットなどでPTSDの代表的な症状にざっと目を通しておくことをお勧めします」
「支援者の方は、もし相手がフラッシュバックしていたら、今、何月の何曜日なのか確認してください。現実感覚を取り戻し、今ここにいることを再確認するのです。そして、相手に対して指示的、あるいは支配的にならないよう、注意が必要です」
「なぜかというと、被害体験を持つ人は相手の加害性にすごく敏感なんです。ふとした行動が、過去、自分を苦しめた相手と重なってしまう。ですから、なるべくフラットな関係を心がけ、日頃の悩みや困りごとを雑談混じりに聞くことが大切です。そして、ミスをしたらすぐに謝ること。アドバイスよりも、こうした取り組みを続け、対等な関係性を保つことが肝心だと思います」
アルコールで破綻した家族。助けられるのは自分だけ

後藤早苗さんは、現在、女性だけの自助グループ、断酒新生会アメシスト埼玉支部の代表として活動している。後藤さんが飲酒の問題を抱えるようになったのは、10代の頃。両親はともにアルコールの問題を抱えており、家でも出先でも常に酔っていた。やがて夫婦関係が険悪になり、母親はパチンコにのめり込む。家にはいつも消費者金融からの電話がひっきりなしにかかってきた。
「自分の家は、ほかの友人の家とは違うんだと思いました。自分がなんとかしないと、家族も母も壊れてしまう」
後藤さんが本格的に飲酒するようになったのは、中学三年生の頃。中学の卒業に伴い部活動もなくなり、暇を持て余した仲間と集まって飲んでいた。
「酔っているときは、みんなが仲間みたいに見えたんです。背負ってる荷物がなくなったみたいで、楽でした」
アルコールは生きるためのガソリン
18歳の頃、父親と姉が見切りをつけて家を出ていった。後藤さんのもとには、アルコール依存症の母親がひとり残された。当時、母親は一人で歩くこともままならず、ほぼ寝たきりになっていた。後藤さんは、アルコールを飲みながら介護を続けた。
「母は、病院に行くことを断固として拒否してました。機嫌を悪くしないように、タイミングを見計らって誘っても、母はなんのかんの理由をつけて『明日行くから』と、先延ばしにする。次第に目も見えなくなり、話すこともままならなくなりました。ようやく聞き取れた言葉は、『こんな体で生きたくない』だったことを、今でも覚えてます」
母親が治療を拒否する一方、後藤さん自身もまた、適切な治療を受けることができなかった。医療機関を受診する機会があっても、アルコールの問題はずっと放置されてきた。
「20代の頃に初めて精神科にかかった時、うつ病とだけ診断されました。私にアルコールの問題があると知っても、医師からは『節酒してください』と言われただけ。自助グループや依存症専門病院の紹介もなく、一方的に節酒しろと言われても、そもそも適正な飲酒量もわからない。これぐらいにしようと決めて我慢しても、結局また飲んでしまう。やめなきゃとは思っていてもやめ方がわからないし、誰もやめ方を教えてくれなかった。自分は意思の弱い出来損ないだと責めて、余計に飲むようになっていました」
そんなある朝、隣の部屋にいる母親が起きる気配がしなかった。疲れ果てていた後藤さんは、そのうち起きてくるだろうと、様子を見に行かなかった。しばらくして、あまりの静かさに不信に思った後藤さんが部屋に入ると、母親は冷たくなっていた。救急車を呼ぶが、駆けつけた救急隊員は、母親はすでに亡くなっていると告げた。
「それからは、ずっと飲み続けていました。飲むというより、摂取する感じ。生きるために飲む。次第に体がアルコールを受け付けなくなって、それでも飲んだ。なのに、だんだん酔えなくなってきて、死にたいって気持ちが止められなくなった」
言葉が出ない自分を、ただ受け止めてくれた人がいた
後藤さんは自殺を試みるが、搬送され病院で一命を取り留めた。ようやく医療につながることができた後藤さんだが、誰も信じられなかったという。長らく、アルコールの問題を看過されてきた影響は大きく、医師にもカウンセラーにも、話す言葉が見つからなかった。転機となったのは、あるケースワーカーとの出会いだった。
「その人は、別に、こっちの心のうちを聞いてこないんです。何を思っているの、どうしたいの、とか、心のなかに踏み込んでこない。ただ普通に人と接してくれた。不思議なことなんですけど、初めてこの人だったら話せるかもと思えたんです」
「入院先の病棟でも、同室の年配の患者さんがすごく優しくしてくれて。若くして入院している人が少なかったこともあって、自分の子どもとか孫みたいに思えたのかも。今までの私の話を聞いて泣いてくれたり、退院後にお花を贈ってくれたり。人として接してくれたことに、癒されたんだと思います」
後藤さんがアルコールを絶って、10年が経つ。今でも、ときどきフラッシュバックに襲われることがある。
「ふとしたことで、母がいた当時に戻ったように錯覚してしまう。母の様子を見なきゃ、とかそういうことが今でも心に浮かぶ。そういう時は、なんとか『今ここにいる』と自分に言い聞かせています」
「思い出すのはつらいですけど、苦しいばかりにならないように、母親が話しかけていると思うようにしています。あの世から、『忘れないで』って言っているんだなって」
後藤さんは、アルコールの問題を抱える仲間の支援を通じて、依存症治療における理不尽さを、少しでも変えていきたいという。
「もっと早いうちに適切な診断や治療を受けられていたら、と今でも思うことがあります。せめて、自助グループの存在を知っていたり、アディクションは意思の問題ではないと知っていたら、もう少し違った経過を辿れたんじゃないかって思うんです」
思い出すきっかけは、悪いこととは限らない
一般的に、トラウマの引き金になるきっかけは、被害体験に関係するモチーフや言葉、状況だと言われているが、後藤さんのケースでは、トリガーが明確なものではなかったり、日常的なことがきっかけになったりしている。野坂さんいわく、「トラウマの引き金となるものは、嫌な出来事とは限らない」という。
「何か悪いことが起きたから思い出す、というものでもないんです。特に幼少期に受けた傷は、これという原因がはっきりしないことがあります。日常的にじわじわと受けた被害の場合、いろんなものが引き金になりやすい」
「喜びや幸せを感じたときに、『きっとまた悪いことが起こる』『うかうか喜んではいけない』と警戒することもあります。いいことが不幸のフラグになっているわけです。こうした自分の引き金に気づくことが大切だと思います」
