アルコール依存症のコミックエッセイを読んで当事者として考えた話(2)
「普通のOL」が朝から常飲するようになったアルコール依存症の当事者コミックエッセイを読んで、自分が飲んできた理由に思い当たったわたし。「依存症」そのものに理解を深める作品にも出会いました。
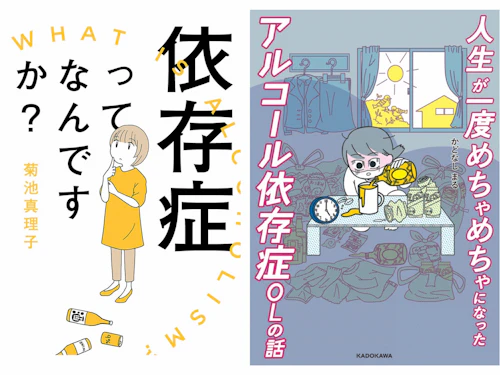
公開日:2024/08/01 02:00
30年間、ほぼ毎日かなりの量を飲んでいたけれど、4年ほど前に「お酒をやめた」わたし。春に上梓した『元気じゃないけど、悪くない』(ミシマ社)の主要なテーマの一つも「アルコールとの関係」でした。
アルコール依存症が「特別な人がなるもの」ではないと知るコミックから、自分にも思い当たることが見えてきたり。
そもそも「依存症ってなに?」というシンプルな問いに答えてくれる作品との出会いから、「お酒と自分の関係」をさらにいろんな角度から見られるようになっていきました。
2回連載の2回目。(青山ゆみこ)
※前編(1)はこちら↓
飲むと「良いヤツ」だったわたし
菊池真理子さんの『酔うと化け物になる父がつらい』(秋田書店)に描かれるアルコール依存症のお父さんを見ていると、「気の弱さから飲む」という印象も強かった。

これはわたし自身、強く思い当たる。
一杯目のビールや白ワインがもたらしてくれる「自分が開放されるような感覚」は、わたしを惹きつけた最も大きなアルコールの魅力だった。
わたしは飲むと非常に陽気で気の良い人になれた(気がした)。
普段は人の目を気にして、小さなことでくよくよし、その場の空気を先回りしすぎて読むほど神経をぴんぴんに張って、そういう自分に疲れていた。
ところが、お酒を飲むとよく言われるように気が大きくなり、多少の失敗もどんまい! なんて明るく笑い飛ばせる「良いヤツ」になれた。そんな自分がとても好きだった。
気疲れして空回りする「オン」の自分と、小さなことがどうでもよくなる器の大きいっぽい「オフ」の自分。
その2つの顔で、わたしは30年生きてきたんだなあ。
お酒に助けられた面もあったんだな。そうだ、助けられてもいたんだ。
普通に働くために飲み始めた女性の、当事者コミックエッセイ
そんなことをふと思ったのは、かどなしまるさんの『人生が一度めちゃめちゃになったアルコール依存症OLの話』(KADOKAWA)というコミックエッセイを読んだ時だった。
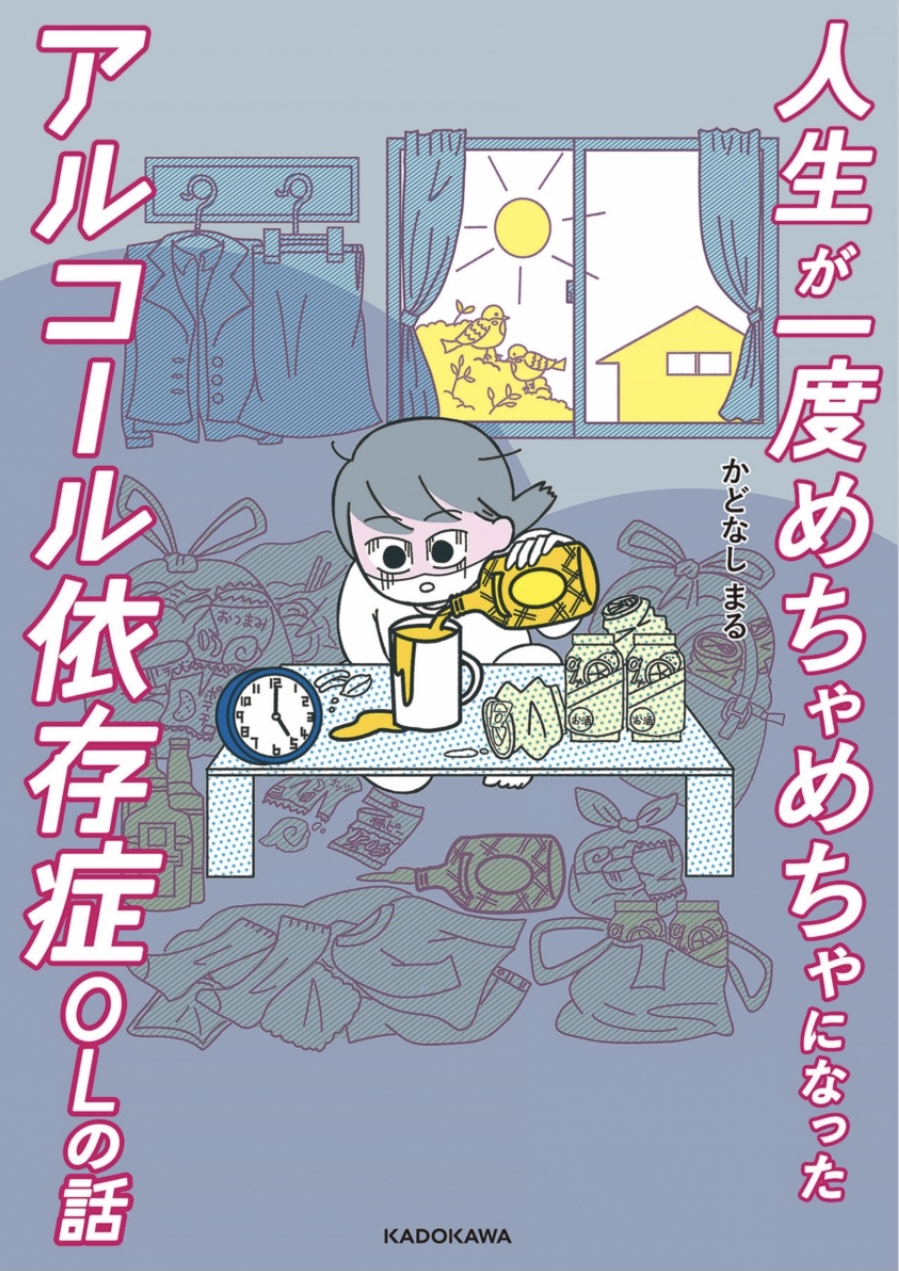
主人公の「まる」さんは、「真面目」で「おとなしく」「かたい」と人からよくいわれる性格。新卒で事務として就職したメーカーは、残業は月20時間ほどでとりたてブラック企業という訳ではない。
ただ、人格を否定して部下を叱責する上司や、労基にパワハラで通報されたことのある女性の先輩や、気に食わないことがあると備品を蹴ったり暴言を吐くギャルの先輩など、かなりクセの強い、ハラスメント体質の温床のような人間関係の職場。
思春期の頃から過緊張で生きづらさを抱えていたというまるさんは、小さなことにびくびくしてしまい、入社1カ月で会社に行くのが魂レベルで嫌になる。
ストレスフルな職場にもう耐えられない。
そんな時、まず飲むようになったのが「不安をやわらげる薬」。就活期からときどき服用していたそうだ。
薬を飲んでだましだましで乗り切っていたものの、夜や休日はストレスやさみしさ、閉塞感からお酒を飲んだくれるようになる。
なぜなら「飲むと心に一枚バリアを張れた感じ」になり、嫌なこともスルーできるようになるからだ。生きづらさを和らげてくれるお酒。
まるさんは、思いついてしまった。
「お酒を飲んだ状態なら、楽に出勤できる気がする」と。
快楽を求めているのではなく、痛みを軽減するために飲む、という感じで。
ページを捲りながら、わたしは「あー、あかん」と思わず呟いてしまった。でも、気持ちはわかる。バレないなら、わたしだって飲んでいたかもしれない……。気が楽になって、良いヤツになれるお酒を。
まるさんは、ある朝、コーヒーリキュールであるカルーアミルクを牛乳に入れて飲んでみた。憂鬱な朝なのに、その一杯で一気に気分はハイになり、電車に乗って出社すると、デスクでさくさくと仕事を片付け、普段ならぴりぴり気が張りまくってびくびく過ごすところが、気楽に時間が過ぎていることに驚いた。
酔いが醒めたあとのテンションの落差はきつかったが、「これなら会社に行ける」と、その日を境に毎朝の飲酒がルーティンになっていく。
「酔う」ための手っ取り早さから、もっぱら選ぶ酒はストロング系のチューハイといったアルコール濃度の高いもの。
時に飲み過ぎて、会社のトイレで吐いたり、ブラックアウトしてしまったり……。
そんなふうに、いわばごく平凡な女性が、遊ぶためでもなく、普通に働くためにアルコールを摂取して、気づけば「人生が一度めちゃくちゃになった」というリアルなプロセスが前半部分。
後半では、試行錯誤を繰り返して、なんとかお酒の力を借りずに生活したり、ストレス発散をする方法を模索するまでが描かれている。
終盤、「お酒と私の危うい関係は一生見張り続ける必要があります」と語られるコマがある。
アルコール依存症は「治る」ではなく、「やめ続ける」こと。
まるさんにしみじみ共感するわたしです(最近スリップした民なので)。
味方になってくれる家族の良い面、難しい面
この本にはまるさんの双子の妹が登場して、一時同居するエピソードが綴られている。妹さんも自身のメンタルに問題を抱えていて、身近な人の影響をどう受けるかも知ることができた。
双子ということもあり、生まれた頃からいつもそばにいた存在がいることは、安心できる心強い仲間という良い面もあるが、関係性が近すぎると、うまくいかないときは、より問題が深刻化するということもある。家族ってやっぱり難しい。
一進一退を繰り返し、なにもかもがすっきりというわけではなく、危うい状況が連続していて、まるさんの行動がまるっぽお手本になるとは言えないだろう。
でも、その時々に切実なまるさんの心境や、自分をなんとかしたいという行動の記録は、たった今、もし「普通の日常生活を送るために」隠れて飲んでいる人がこれを読んだら、仲間に出会ったようにどこか救われるかもしれないし、今までと異なる行動をするきっかけになるかもしれない。
やや自虐的に、リアルに描かれているので、読んでいて苦しくなる部分もあるけど、「正しさ」で詰められるような圧はなく、読めるんじゃないかと思う。
正論はわかっていても、そう簡単にうまくいかない、ままならないのが依存症の現実だ。まるさんのトライ&エラーの軌跡に、そのことがすっと腑に落ちる。
そもそも「依存症ってなんだ?」
いちおうはお酒をやめたわたしだが、やめたらすっきりという訳ではなく、むしろ飲んでいた頃の自分を過度に責めたり、前編で話したように、今もアルコール依存症に対して複雑な思いを抱いている。
そもそも「依存症ってなに?」というシンプルな疑問を改めて抱くようになった時、大きく示唆を受けたコミックエッセイが、アルコール依存症のお父さんを漫画で描いた菊池真理子さんの『依存症ってなんですか?』(秋田書店)だった。
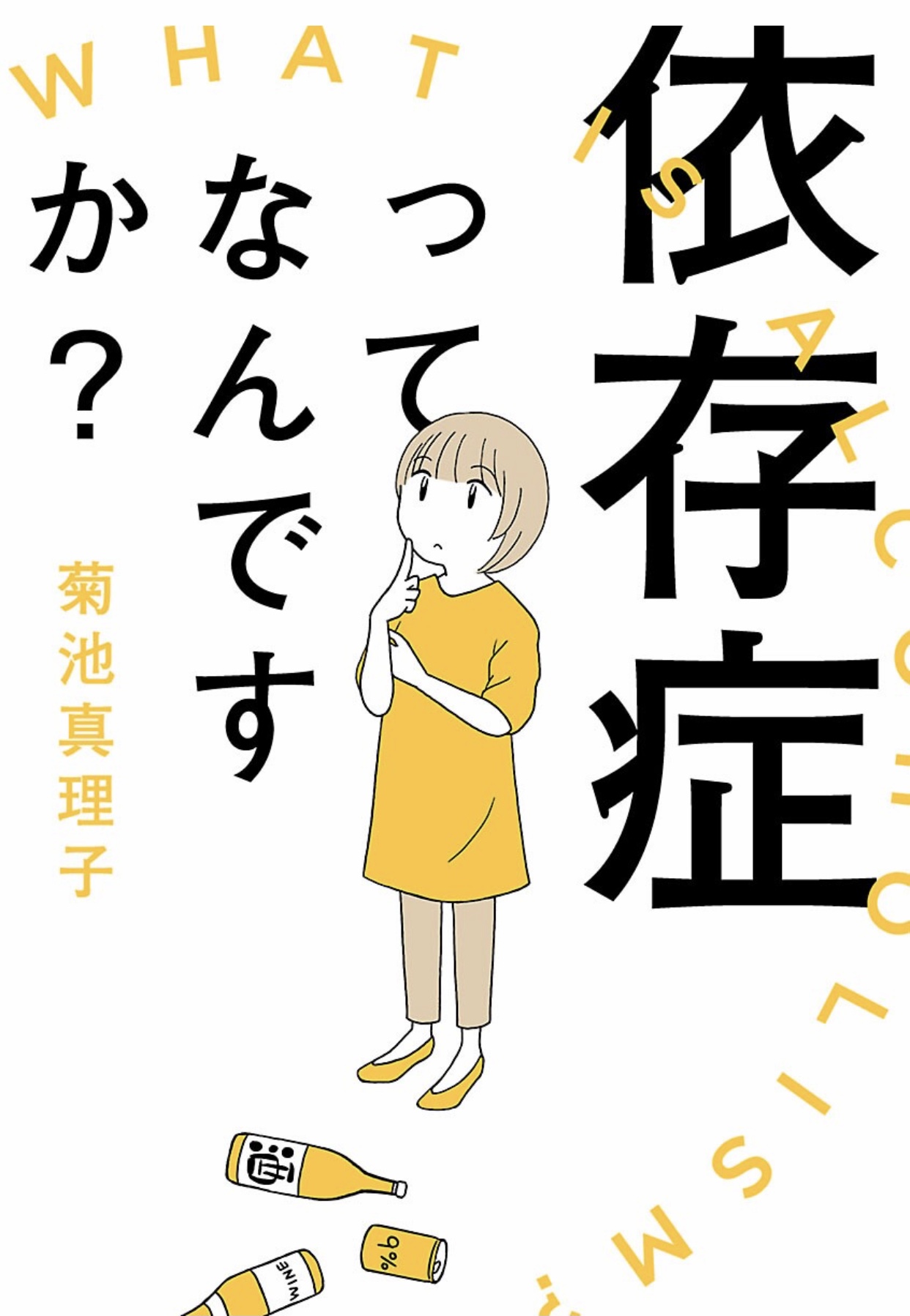
「父はなぜお酒をやめられなかったのか」
この本は、菊池さんのお父さんが亡くなって一年が過ぎた頃、どうしてもわからなかった父の飲酒行動の謎を解くように、いろんな人に取材しながら、少しずつ「依存症」について理解を深めていくというルポ作品ともなっている。
日本の二大自助グループである「断酒会」と「AA」を訪ね、自分の病に向き合う人たちに出会う。その優しい空間で、菊池さんは初めて依存症の人たちが好きになる。
また、アルコール依存症の親をもったことで生きづらさを抱えているアダルトチルドレンの自分にヒントを探すべく、カウンセラー(信田さよ子さん)の元にも通い始めた。
みんなどうやってお酒に向き合っているの。
お酒の問題をどう考えたらいいの。
まるで菊池さんが、読者であるわたしの疑問を、テーマごとに一章ずつ紐解いてくれるような構成だ。
重度のアルコール依存症に苦しんでいたが、現在は「お酒をやめ続けている」ZIGGYの森重樹一さんに話を聞きに行く章では、「父」でもあるアルコール依存症当事者の話を聞くことが、自分に「悪くなく影響する」ことに菊池さんが触れているのも印象的だった。
「娘をACにしたくなかった」と語る森重さん。その言葉を聞いて、自分が親の飲酒による機能不全家庭で育ったACであることが、すとんと胸に落ちて、それが全然悲しくなかったという。
その場面では、わたしはまるで、森重さん、菊池さんの参加する自助グループにでもエア参加しているような気持ちになった。本を通しても、深く心に触れてくるものがあるのだなあ。
また、このくだりを読んでいて、「誰かの話で変化する人の姿を見る」ことも、大きな意味があるように感じた。
言葉が一方通行になるのではなく、双方向に影響し合う、複数の人が集まる場には、思っている以上に力があるのかもしれない。
立場によって見え方が変わる依存症
医療現場の専門家を訪ねて、さらに依存症について理解を深める菊池さん。
楽物依存症に長く携わっている松本俊彦先生からは、改めて「依存症が病気である」ことを学ぶ。
「絶対に怒らない、責めない」で「生きづらさ」の支援をする成瀬暢也先生からは、アルコール依存の人にとってお酒が命綱という考え方を知る。それがあるから生きていけるというものだと。
命綱か。
わたしもお酒があったから、どんな時も生きてこられた気もする。ずいぶんと助けられたよなあ。
成瀬先生は、減酒という方法の可能性や、早い段階に治療や支援につながれば、大切なものを失わずに上手にお酒と付き合っていくこともできるとおっしゃっている。
こうしたことを知っているだけで、なんだか少し気が楽になる。知識ってやっぱり大事だ。
菊池さんは、回復や社会復帰の支援をするダルクを訪ねたり、日本初のアルコール依存症専門病棟を設立した久里浜医療センターの看護師さんといった現場の支援者にも話を聞きにいく。
もし、たった今、自分が、家族がアルコールで困っている人には具体的な支援先を知るきっかけにもなると思う。
支援者への取材は、依存症当事者が吐露する声を間接的に耳にする機会ともなっている。当事者の声は、そばにいる家族には、実はもっとも聞こえにくいものなのかもしれない。
家族としてできたこと、家族だからできなかったこと。
依存症を客観的に理解し、自分の体験をどこか俯瞰して見られるようになってきた頃、菊池さんがこんなことを呟く。
「依存症ってやっぱり立場によって見え方が全然違う」
わたしは今も、まだアルコールに対して複雑な思いがあり、つまりまだまだ囚われている。
それでも、少しずつその囚われから解き放たれていくように感じているのは、「見え方が変わって」きているからだと思う。
やめた直後は、自分の過去の飲酒に対して、蓋をして見たくない気持ちが強かったけれど、最近は少しずつ角度を変えて眺め直すこともできるようになった気がしている(テンションが低いときには絶対にやらないが)。
しんどい気持ちの強かった家族の飲酒に対しても、同様に。
菊池さんがいろんな人を訪ねて、聞いて、話を重ねたように、自分ひとりでは見えないものを、わたしも誰かに教えてもらいながら見ていこうと思う。そんなヒントも菊池さんにいただいた。
最後のページに描かれた菊池さんが自分に向けたメッセージは、とても優しくあたたかい。笑顔の絵が心に残る。しんどくなったら思い出そうと思う。
(おわり)
関連記事
コメント
誰かの話で変化する人の姿を見る、ことが希望だった。
依存症の人が好きになった。
まるで自分の話しのよう。
私は「家族としてできたこと、家族だからできなかったこと」を経験し「家族だからできない、家族としてできること」に変えて生きているんだな、と記事を読みながら、改めて思いました。
「依存症ってやっぱり立場によって見え方が全然違う」
青山さんから見る依存症が、私にはない視点でドキッとします。そんな2連続記事でした。
