先生、「治療する裁判」ってなんですか? ~再犯を防ぐ「治療的司法」とは~
刑務所新規入所者の半数以上を占める薬物の自己使用と窃盗。回転ドアのように再犯を繰り返しては刑務所に戻ってくる彼らに必要なのは、刑罰ではなく治療や福祉なのでは?
負の回転ドアを止める「治療的司法」とは何か、法学者の指宿信教授に話を聞いた。

公開日:2025/05/08 02:00
ーーああ、この人また薬物で捕まったのか。再犯なら、実刑は免れないな。
私は前職で弁護士事務所にパラリーガルとして所属し、刑事事件にも携わっていた。当時、依頼が来る刑事事件といえば、窃盗と薬物ばかり。調書に前科や余罪が記載されていることも珍しくない。当たり前すぎて、疑問にも思わなかった。
なぜ彼らは何度捕まってもまた手を出してしまうのだろう。回転ドアのように、刑務所から出ては入ってを繰り返す再犯者にとって、刑罰は本当に意味があるのか。
もし、刑罰以外に窃盗や薬物使用の再犯を止められる方法があるとしたら?再犯・実刑の無限ループを断ち切る「治療的司法」を提唱する、刑事訴訟法学者の指宿信教授にお話をうかがった。
もし逮捕されたらどうなる?
ーー「治療的司法」は初めて聞く概念なのですが、「依存症が原因で罪を犯してしまった人に対し、刑事罰よりも治療を優先しようという考え方」、という理解であっていますか?
その通りです。
まず、日本の刑事手続きには、3つのルートがあることは知っていますか?
①通常の刑罰ルート
②障がいや精神疾患などがある人のルート
③少年のルート
ある意味、日本では既に②や③によって治療的司法を取り入れているともいえるんです。私たちは、依存症のように自分の行動を自分の意思でコントロールできない人に対し、①のルートにもう一つ別のルートを用意して、刑罰ではなく治療につなげようと訴えています。これが「治療的司法」の考え方です。
ーー現在の刑事手続きは、どのように進んでいくのでしょうか?
まず、犯罪が発生すると、被疑者(犯人)は身柄を拘束され、警察官から取り調べを受けます。さらに検察庁に送られて検察官から取り調べを受け、ここで起訴・不起訴が決まります。起訴の場合は、裁判手続きが始まります。
裁判で執行猶予がつかず実刑となった場合は、刑務所に収監されます。そこで刑期を過ごして出所するというのが一連の流れです。
この流れに、最近では国もようやく再犯防止に目を向け始め、「入口支援」、「出口支援」を開始しました。
ーー「入口支援」、「出口支援」とはどういったものですか?
不起訴で「刑務所行き」を免れた人のなかには、社会復帰に困難を抱える人もいます。そういった人たちを必要な福祉・医療サービスにつなぐ支援を「入口支援」といいます。
逆に、「出口支援」とは、実刑になって刑務所に入った人が、出所後スムーズに社会復帰するための支援です。出所前に居住先の確保や就労支援などを行っています。
.png)
懲役刑がなくなるって、本当ですか?
ところで、日本の刑務所は敷地の8割が工場だと知っていますか?日本の収監者は「懲役刑」、つまり、収監されて強制的に働かされるという強制労働の刑を受けています。受刑者が働く場所が、敷地内の工場なんですね。実はこれ、国際的には「人権侵害だ」と批判されているんです。
ーー確かに、受刑者が作った家具などが販売されていることは知っていましたが、「人権侵害」だという認識はありませんでした。受刑者に労働を課すことで、気分転換や生きがいにもつながるのかと。
確かにそういった一面もあるかもしれません。しかし、たとえば、薬物の自己使用で依存症治療が必要な方が収監されても、月曜日から金曜日まで働かされれば治療の時間が確保できませんよね。
刑務所にいる間はクスリとの関係を絶つことができますが、依存症治療ができていないので、出所後すぐに再犯に至ってしまうんです。治療や教育の時間を確保しやすくするには、強制的に労働する仕組みを変えるしかありません。
2025年5月末で懲役刑と禁錮刑が廃止され、6月より拘禁刑に統一されることになったんです。
ーー懲役刑がなくなるのですか!?
これによって刑務所側は、新しく「拘禁刑」を言い渡された受刑者を、働かせることもできれば、治療することもできるようになりました。これは小さな進歩だと思います。
ただし、私たちが主張する第4のルートができたわけではなく、あくまで「刑罰ベース」の考え方による改正です。
日本の裁判所では「行為責任主義」が浸透しており、この行為にはこの刑罰、と自動的に判定する裁判官が多くいます。覚せい剤の再犯なら実刑、と機械的に決めてるんですね。
これに唯一メスを入れられるのが、弁護士です。
事件発生後、警察の次に被疑者に会うのは弁護士です。そこで我々は、弁護士に対する研修に力を入れてきました。接見の際には被疑者に治療が必要か否かを判断し、実際の裁判では効果的な情状弁護ができるようになってもらうためです。
海外で実践される「問題解決型裁判所」
ーー先生が目指す「第4のルート」を実際に採用している例はあるのでしょうか?
アメリカやカナダ、オーストラリアなどの欧米諸国では、依存症などの問題を抱える犯罪者に対する特別な司法システム、「問題解決型裁判所」があります。「ドラッグコート」(薬物専門法廷)が代表例ですね。これが、私たちが目指す第4のルートです。
海外の裁判官は、日本と違ってほとんど異動がありません。その地域に根差しているので、自分が判決を下して収監した被告人が、出所後しばらくしてまた同じ犯罪で自分の前にやってくるという経験を何度も繰り返します。
この現象を彼らは「スライディング・ドア(回転ドア)」と呼びました。依存症による犯罪には刑罰は意味がないと、彼らは悟ったんです。
依存症による犯罪者は、自分の行為を自分でコントロールできません。彼らを刑務所に送るのではなく、治療することで行動のコントロールを可能にし、再犯を防止しようと考えたのです。
ーーその「問題解決型裁判所」とは、どんな手続きなのでしょうか。
「問題解決型裁判所(Problem Solving Court:PSC)」では、被告人に刑罰を与えるかどうかを決定するのではなく、被告人の抱える依存という問題の解決を目的とします。
通常の裁判のように裁判官、検察官、弁護人、書記官がいて、これに加えて、コミュニティの代表としての警察官、ソーシャルワーカー、場合によっては臨床心理士なども参加し、本人の生活態度や薬物テストの結果をシェアして治療プログラムを決め、定期的に本人を呼んでその進捗を確認します。
厳しい裁判官などは、違反があると短期間収監を命じることもあります。
そのようなプログラムを年単位で時間をかけて、治療していきます。問題解決型裁判はあくまで任意なので、この手続きを選ばず刑事手続きによる実刑を選ぶ人もいます。刑務所に入って刑期を満了した方が、よっぽど短く楽なのかもしれませんね。
ーーどんな方が対象なんですか?
欧米では、ドラッグ依存やギャンブル依存、アルコール依存などによって犯罪行為に及んだ人が対象となります。その他、退役軍人でPTSDなどを発症し、ドラッグやアルコール依存になったことで犯罪に至った人に対するベテランズ・コート、売春行為や薬物依存に陥った少女に対するガールズ・コートもあります。
また、アメリカにはドラッグやアルコール依存などで交通事故を犯した人に対する「問題運転コート」という問題解決型裁判所があります。
そこで更生した最も有名な人が、プロゴルファーだったタイガー・ウッズです。彼にはアルコール依存と合法薬物の依存がありましたが、「問題運転コート」の手続きによって立ち直ったのです。
でも「犯罪者にそんなお金をかけるな」って言われそう……
ーー「問題解決型裁判所」、とてもいいアイデアだと思います。しかし、犯罪者にそんなお金や労力をかけるのか、という声もあがってきそうな気がします。
いわゆる、被害者感情と納税者感覚からの反対意見ですね。これについてはしっかりと解決できます。
まずは被害者感情について。その事件の被害者の回復は難しいかもしれませんが、依存症を治療し再犯を防止すれば、第2、第3の被害者を出さずにすむでしょう。
それに上で挙げた問題解決裁判所の例でわかるように、こうした裁判所が対象とする犯罪は多くが被害者のない犯罪です。
そして、納税者として犯罪者にお金をかけるなという意見について。実は、依存症による犯罪者を収監するよりも、治療する方がはるかに金銭的負担が軽いのです。
ひとりの犯罪者を1年間収監するのには、400万円以上の費用がかかるといわれています。治療によって再犯者の一部でも回復させることができれば、その分税金による支出を削減できるのです。
また、問題解決型裁判所が多く作られている米国でも、刑務所に送られた場合よりも実刑を回避し治療を受ける手続きを修了した方が、再犯率がずっと低いことがわかっています。社会にとっても安全につながり利益が大きいということになります。
ーーつまり、依存症治療によって出所と収監のループを断ち切れば、収監費用が発生しなくなり、その分国の経費負担も減るということですね。
そうですね。日本の刑務所には、依存症によって出所と収監を繰り返している人がある程度いると予測できます。それは、犯罪白書などを見れば明らかです。
たとえば現在、日本の受刑者のうち、窃盗と薬物の自己使用が全体の半数以上を占めています(令和5年版犯罪白書)。そして、新受刑者のうち約6割が再入所者なのです(再犯をめぐる近年の動向)。
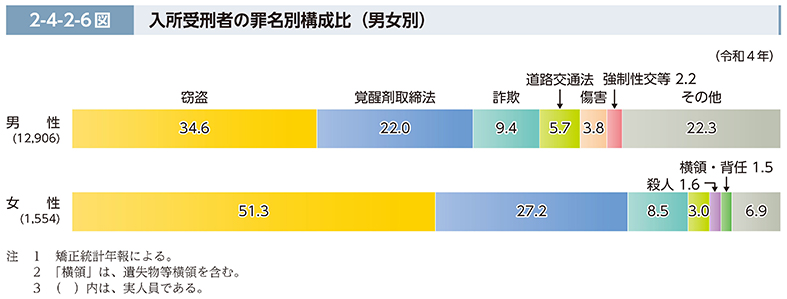
.png)
ーー薬物犯罪はわかりますが、窃盗も依存症によって引き起こされるのでしょうか?
依存によって万引きを繰り返す「クレプトマニア(窃盗症)」の存在はあまり知られていないかもしれませんね。
侵入を伴わない窃盗のうち約70%が万引きです。ですから窃盗再犯のうち、一定数はクレプトマニアで治療を必要としている人がいる可能性が高いんです。また、高齢者の万引きは貧困により引き起こされることがよくあります。
彼らは恥ずかしくて生活保護を申請することができず、万引きに走ります。
クレプトマニア(窃盗症)には治療が必要で、貧困による万引きには福祉によるサポートが必要なのです。
私は早く日本に第四のルートを作りたい。まずは「覚せい剤コート」と「万引きコート」を作る必要があると考えています。
依存症による犯罪は、刑罰では救えない
ーー先生はいつ治療的司法という考え方に出会ったのですか?
私が初めて「治療的司法」という考え方を知ったのは、2006年当時勤務していた大学で、カナダの裁判官マリカ・オーマツさんの講演を通訳したときでした。そのとき初めてドラッグコートの存在を知り、発想の転換があったんです。
ーーそれまでは司法制度に対して、課題感はなかったのでしょうか?
正直、違和感はありました。刑事訴訟法の研究者として法廷を見学に行くと、覚せい剤の事件ばかりなんです。しかし私も「またヤク中か」で思考停止していたと言わざるを得ません。
依存を取り除いてあげるのも刑事司法の責任だとは、思っていなかったんです。それは俺たち(法律家)の仕事じゃないと考えていたのでしょう。
オーマツさんから治療的司法の考え方を学んで以来、その制度を日本でも導入すべく活動してきました。国に研究費を申請して仲間を集め、2017年にこの治療的司法研究センターを創設したんです。
今ではだいぶ私たちの活動に賛同してくれる弁護士も増えました。彼らも心のどこかで違和感を抱いてきたはずなんです。依存症による犯罪は、刑罰では救えないと。
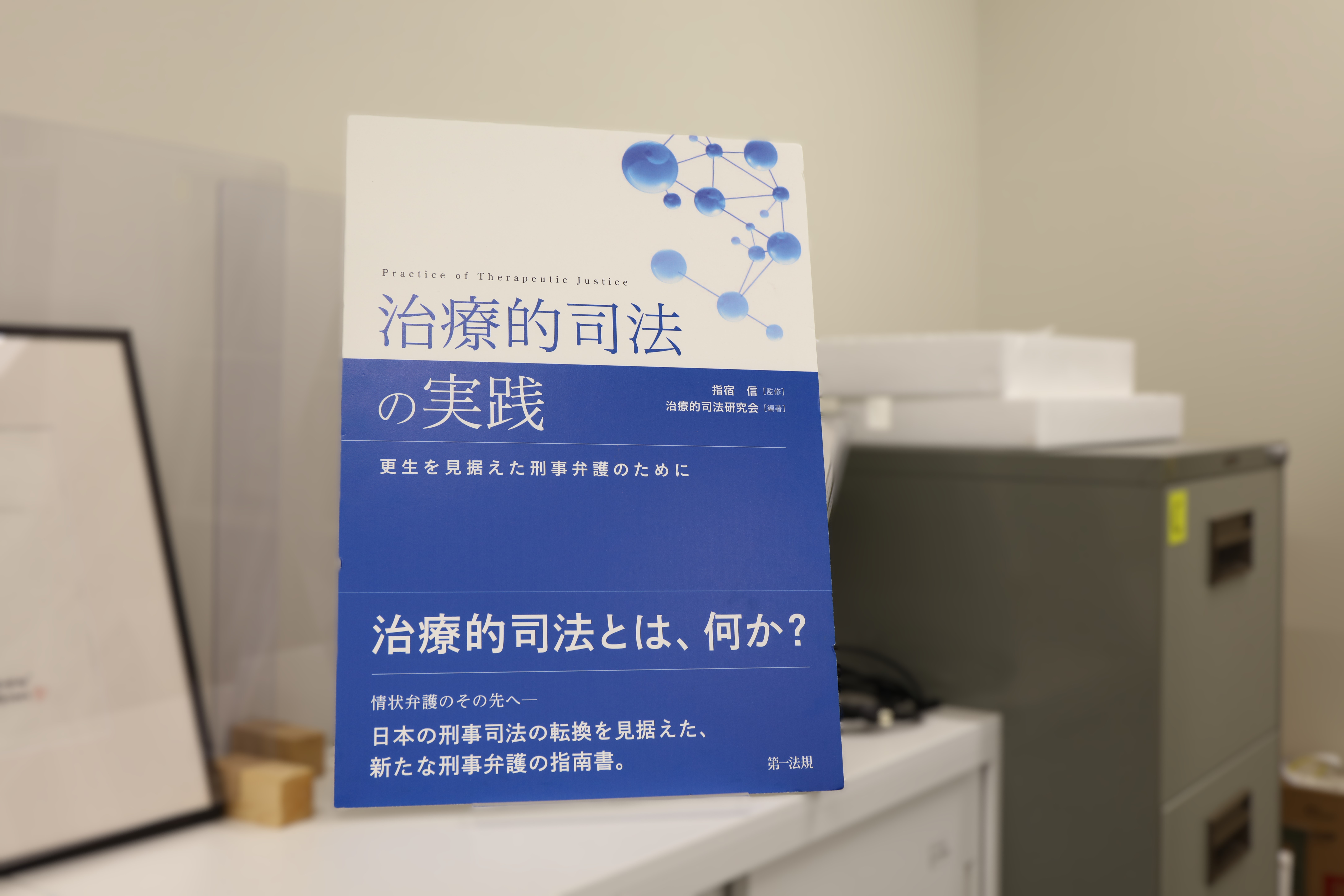
依存は人間の生存戦略
ーー一部でドラッグの自己使用を犯罪とすべきではないという考え方もありますが、先生はどう思いますか?
私も同意します。問題は、ドラッグを使用することではありません。依存症なら、アルコールが最も体に悪く、周囲に危害を加える可能性も高いといわれているんです。
一番目を向けなければならないのは、なぜアルコールやドラッグに依存する状況に追い込まれてしまったのかということ。本人を犯罪者にしてさらに追い詰めるのではなく、犯罪に至った環境や社会の仕組み、本人の抱える問題そのものに目を向けるべきでしょう。
ーー薬物依存の問題は、本来司法が動く前になんとかすべきですよね。
その通りです。しかし日本では「ダメ。ゼッタイ。」を掲げているので、本人を救えません。本当は、なぜ薬物に頼らざるを得なかったのか、その原因に公的資金を投入すべきなのです。
「ダメ。ゼッタイ。」を掲げている限り、薬物に手を出してしまった人は治療にブレーキをかけてしまいます。依存を隠してしまうので、治療に繋がらないのです。
ーー依存症の人が、発覚を恐れて治療に向かえないのですね。
人間は、いろんなものに依存して生きているのだと私は思います。薬物やアルコールだけじゃない。ニコチン中毒もあれば、ワーカホリックもあるでしょう。あなたも何か依存することはあるでしょう?
ーー確かに、原稿の〆切が重なったときには、ダメだとわかりつつ、日に何本も栄養ドリンクを飲んでしまうことも……。
国が薬物ではなく、栄養ドリンクを規制していたら、それは犯罪行為です。しかし、やらなければならないことをやりとげるために栄養ドリンクが必要なのですよね。薬物使用者も同じです。
私が出会った薬物使用者のなかで、20年以上薬物と「いいお付き合い」を続けている方がいました。依存症になることもなく、幻覚や幻聴などの副作用もなく、ただ仕事で忙しい時期を乗り越えるときだけ禁止薬物を服用していたといいます。会社から見たら、ただ「仕事のできる社員」に見えたでしょう。
法が薬物を禁止しているから、薬物依存は犯罪者だと非難されてしまうだけなんです。
ーーなるほど、お酒、タバコ、カフェイン、仕事、人間関係……。確かに私たちは何かに依存して生きているといえるかもしれません。
依存症には、「自己治療仮説」という仮説があるんです。生存し続けるために、何かに依存することで自分を治療しているという考え方です。まだ仮説ですが、この説に当てはめると、全ての依存症についての説明がつくのです。
生き続けるためにリストカットをする、生き続けるために薬物を摂取してDVに耐える。
生存か死かのすさまじい瀬戸際で、何かに依存することで生き続けている人がいる。
依存というのは、人間の生存戦略のひとつなんです。
(終わり)
【指宿信(いぶすき まこと)】成城大学教授、治療的司法研究センター センター長
1959年生まれ。法学者。鹿児島大学、立命館大学を経て、2009年4月より成城大学教授。専門は刑事訴訟法。取り調べの可視化、刑事司法のIT化など、刑事手続の改正に尽力。2017年より治療的司法研究センターを立ち上げ、センター長に就任。犯罪者の心理的・社会的な問題を解決することで再犯を防止する司法的取り組み「治療的司法」の実現を目指している。著書に「証拠開示と公正な裁判」(現代人文社)、「治療的司法の実践」(第一法規)など
【訂正】「2025年4月から懲役刑が廃止された」と書きましたが、正しくは「2025年5月末で懲役刑と禁固刑が廃止され、6月より拘禁刑に統一される」でした。訂正します。
コメント
二度、クレプトマニアで性的嗜好犯罪で刑務所に収監された者としての感想と意見を言わせて頂けるなら、私は刑事罰は有るべきと感じます。
病気だからといって犯罪が許されるべきでは無いと思うからです、
罪を犯した償いと反省は必要です。
工場での作業が余りにも単純でノルマも無くただ、時間をやり過ごせは良い。 悔いて反省し新たな人生を歩もうとしても社会は簡単には、許さないし働く事も出来ない。
ウッズさんが回復したのは、プログラムに参加出来た以上に生活出来る資金が合った筈。
社会にほうり出され仕事にも就けないでは、悔い改めて新しい人生を歩み出そうとする意欲が失われます。
治療を優先する前に社会で仕事に就ける事です。仕事をしながら治療プログラムを受け回復を進めるのが当事者として望んでました。
私の様に身内も頼れる者もいない者は、生活保護に頼るしか生活が出来ない。しかし、その申請を知らない者、恥と考える者にはハードルが高い。申請に辿りつけても受理されない者は、短期労働者とか、生活保護申請代行悪徳業者に騙されて保護費の殆どを搾取されたりすれば、希望は無くなり再犯に至ります。
社会復帰と仕事、生活出来る資金が有ってこそ、治療に繋がる。
刑務所内で治療を受けられても社会復帰した後生活出来なければ、治療は役に立ちません。
希望を失えば再犯します。
国は刑務所と連動した社会復帰事業を両輪で行うのが望ましいと思います。
民間が関与し立ち直りを支援する。
メディアを利用し社会に広める。
それでも再犯者は少なからず出ます。それでも意義は有ると思う。
