あなたはなぜ大麻を使うのですか? 「意思が弱い」「反社会的」というイメージとはかけ離れた実態が明らかに
大麻を使うのは、意思が弱いから?反社会的だから?大麻使用者のインタビューを分析した研究で、世間のイメージとはかけ離れた実態が明らかになりました。
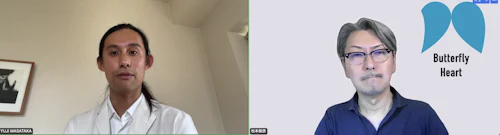
公開日:2025/08/11 08:04
違法と知りながら、大麻を使うのは意思が弱いから?反社会的な人物だから?
日本社会ではそんなイメージが蔓延している大麻だが、それは真実なのだろうか。
そんな問いを検証した日本発の論文が7月、薬物関連の学術誌に掲載された。
大麻利用者64人のインタビュー調査から見えてきたのは、生きづらさや不調を和らげたり、生活の質を上げようとしたり、ネガティブなイメージとはかけ離れた実態だ。
Addiction Reportは、研究にあたった一般社団法人、GREEN ZONE JAPAN代表、正高佑志さん、国立精神・神経研究センター薬物依存研究部長、松本俊彦さんに取材した。
64 人のインタビュー記事企画を事後分析
イギリスの学術誌「Drug Science, Policy and Law」に7月24日に掲載された。
2021年6月から23年4月にかけて、日本の大麻使用者の実態を把握しようと行われたインタビュー記事企画「Cannabis User Interview Project(CUIP)」のデータを事後分析する形で行われた。
このインタビューは、1. 大麻使用のきっかけ、2. 大麻使用を継続する理由、3. 大麻使用による影響について聞く形式で行われたものだ。
対象者はSNS上で募集され、男性39人、女性25人が参加した。そのうち20 代が 32 人(50%)、30 代が 11 人(17%)と若い世代が多く回答している。
生きづらさから使い始める人も
分析の結果、参加者のうち 29 人(45.3%)が、10 代から大麻を使い始め、使い始めたきっかけは、友人、先輩、恋人など親しい人物からの勧めと回答した人が53 人(82.8%)とほとんどだった。多くは、好奇心や周囲との関係性から始めていたが、いじめや虐待、家族関係の不和、仕事上のストレスなど、何らかの生きづらさから使い始めたと回答する人もいた。
「学生時代ずっといじめられていて、精神的に参っていました。社会人になっても、職場で周囲に無視され、上司にも相談できず孤立していきました。当時は市販薬や安定剤を乱用していて、ドアノブで首を吊って自殺しようとしたこともあります。先輩に『死ぬ気なら一度吸ってみたら? 少しは楽になるかもよ』と言われたのがきっかけです。」(20 代女性)
使い続ける理由として最も多かったのは、不安やうつ、不眠、痛みなどの健康上の問題への対処法としてだった。他に、娯楽や食欲促進、処方薬の代わりに使っている例もあった。
また、大麻の精神作用で音楽や食べ物などに対する感覚が鋭敏になり、生活の質が上がったと答える参加者も多い。コミュニケーションを円滑にする効果や、集中力や創造力の増進、リラックス効果やストレス緩和を求めて使っている人もいた。
「マリファナを吸っていると、子どもの頃に毎日感じていたような喜びや満足感をまた味わえます。朝の散歩とか、音楽を聴きながら過ごすのがとても心地よく、ポジティブに一日を過ごせます。」(20 代男性)
「普段は慎重で内気な方なんですけど、マリファナを吸うと自然体で話せるようになるし、見た目も気にならなくなる。会話が楽になります。」(20 代男性)
「私は映像編集の仕事をしていて、ハイの状態だと細かいところに気づけるので、クオリティの高い作品が作れます。冷静な時には見えなかった角度からも物事を捉えられるようになります。」(20 代男性)
処方薬や市販薬の代わりとして使い、自己治療のような側面も
さらに複数の人が、処方薬や市販薬、アルコールの代わりに使い、そうした薬物の乱用や依存から逃れられていると答えていた。
「いくつもの心療内科を転々として、大量に処方薬をもらっていました。治療のためというより、ただ多幸感を得るために乱用していた。でも、マリファナを毎日使っていた時期は、処方薬は一切使っていませんでした。」(30 代女性)
また、複数の参加者が医療目的で使用しているとし、抱えている病気で最も多かったのは、うつ病、不安障害、不眠症などの精神疾患だった。慢性の痛みなどに対して使っている人もおり、多くの参加者が従来の薬よりも効果を感じていた。
「一度、『どうせ死ぬなら』と思ってマリファナを試してみました。すると、頭痛や吐き気、不安といった精神薬の離脱症状が劇的に軽減されました。生きていける気がした。安定剤でも効かなかった症状が消え、便秘が治って食欲も戻り、人生が明るくなった。自然とお酒もやめられて、人と酒なしで関われるようになった。母も、もう『死にたい』と言わなくなった私を見て、喜んでいます。家事も風呂も何もできなかった私が、ちゃんと生活できるようになりました。」(30 代女性)
「ひどい片頭痛があったけど、インディカ種を使うと痛みが和らいだ。薬はなるべく使いたくないので頭痛薬は避けてたけど、マリファナを定期的に吸うようになってからは、頭痛が出なくなった。」(20 代男性)
「以前はうつ病の薬を 11 種類も飲んでいて、まるでゾンビのようでした。感情が出せず、人の言うことも理解できなかった。数字は見えても意味が分からなかった。そんなときに、友達がマリファナをくれて、吸ってみたらすごく楽になった。今では薬は 2 種類だけになりました。」(60 代女性)
育児や生活上のストレスを緩和するために使っている人もいた。
多くの人は違法薬物である大麻を使うことについて、当初は不安や罪悪感を抱いていた。しかし使ううちに、たばこやアルコールよりも害が少ないと感じるようになる人が多く、多くは日常生活への支障は少ないと考えていた。
またほとんどの人は口の乾きなどの軽度な副作用しか経験しておらず、大麻で最も大きなデメリットは違法性によって逮捕されることであると感じていた。
さらに、大麻を使うとより強い薬物を使うようになるとする「ゲートウェイ仮説」については、自身の体験から否定する人が多かった。
「私はマリファナで満足していたので、他の違法薬物を使おうと思ったことはありません。ゲートウェイ・ドラッグだとは思いません。」(30 代女性)
「マリファナは入り口だってよく言われるけど、それが本当なら、私はとっくに覚醒剤に手を出しているはず。でも、そんなことはないと思います。」(40 代女性)
データでこぼれ落ちるものを拾う
分析対象となったインタビュー企画を始めたのは、正高さんらの研究グループが行っている大麻に関する大規模なアンケート調査ではこぼれ落ちるものがあったからだという。

「データ上では、大麻で依存症になる可能性のある人は9%前後で、大麻精神病など深刻な事態に陥る人はほとんどいないことなどがわかるのですが、なぜ依存症でもないのに大麻を使い続けているのかわからない。一見不合理な違法行為をなぜ続けるのかがよくわからなかったんです」
「よく厚生労働省や警察がやる薬物教育の漫画などは、いつも似たようなストーリーが語られます。ごく普通の真面目な学生が、悪い先輩や友達に誘われて、興味本位で大麻を使ってしまうとすぐに依存に陥り、取り返しのつかない破滅へ至る——。本当にそうなのか、リアルな物語を掘り起こそうと考えました」
松本さんも、こうしたインタビュー分析の意義をこう語る。
「一連の大規模なアンケートによるデータ分析を補完する最後のピースの1つだと思います。ある事象の実態を把握する時に、たくさんの数を集めてマスで見ることはとても大事ですが、それによって個別性や実態の近景は失われてしまう。そこを補完するために、ナラティブ(個別の語り)を丁寧に拾っていく作業は絶対に必要です」
逮捕はより困難な状況に追い込むこと
今回の分析をして、正高さんは公的に語られている大麻使用者のイメージとは違う部分をこう指摘する。
「継続して使用している人たちは、深刻な事情がある人が多い。処罰が厳しいことはわかっているのに使うのは、リスクを超えるメリットがあるから。印象としては、診断は受けていないけれど、精神科に行ったら発達障害やパーソナリティ障害と診断されるのではないかと思える人が多い。その生きづらさを何とかするために、大麻を使って暮らしているのではないでしょうか」
「そんな人から大麻を取り上げるだけでなく罰則を加えるのは、より困難な状況に人を追い込んでいるのではないか。こういう人を逮捕して刑務所に入れるのは酷な話だなと改めて感じました」
松本さんは、大麻使用者が、司法の枠組みでは「社会の規範を犯した人」、医療の枠組みでは「健康を害した罰当たり者」のようにだけ語られてきたことに疑問を投げかける。
「自助グループで回復者が自身の過去の体験を語ることにはもちろん敬意を抱いていますが、一方で、医療や司法の価値観から離れて、回復や薬を止めることを目指さずに使い続けている人のありのままの物語を知ることもとても大事です」
「医療の枠組みは『健康至上主義』になっているので、例えばタバコを吸うことがいかに使用者を助けてくれるか、医学論文で書くのは難しい。違法と位置付けられていることもあって、大麻はさらにそういうことを言うのは難しい。だからこそ、フリーな立場で思いを語ってもらったこの研究は貴重です」
ただ、このインタビュー企画は、大麻使用に否定的ではない団体の呼びかけで行われたこともあり、参加した64人にバイアスがかかっている可能性は否定できない。しかし、松本さんは「大規模なアンケート調査で描かれた大麻使用者像と一致する」と評価する。
そして、今回の分析結果から、医療や司法の枠組みで言われてきた「大麻関連の精神障害」を見直す必要性も感じているという。
「大麻そのものの影響というよりは、社会が大麻使用を反社会的とか犯罪と見ているため、使ってしまったことに罪悪感を抱いたり、糾弾されるんじゃないかという不安の中でパニックを起こしたりする。今回の研究が、薬物の影響を、薬理作用だけでなく、社会の中での扱われ方によって何が生じているかを議論するきっかけになったらと思います」
「いろんな生きづらさや困りごとを抱えて、大麻をセルフケアとして使っている人たちは、日本社会でのルールに違反しているのかもしれません。しかし、それを犯罪として刑罰の対象にすることが民主的な国家において本当に正しいことなのか。実名報道するほど悪いことなのか、問い直したい」
そもそも他の違法・合法薬物と比べても、大麻は依存性や健康への有害性は少ないと見られている。
正高さんは「大麻を使い続けることによる体や精神への負担は、アルコールよりは軽いと考えられますし、世界中の科学的調査の結果もそれを示唆しています」と語り、大麻の社会的な位置付けが大麻使用者を追い込んでいる側面があると語る。
「大麻が違法である日本で使うことは、自分を犯罪者として置き続けることになるので、逮捕によるダメージ以外にも、社会的な吹き溜まりへ人を連れていくような影響がある。違法な薬物を使うコミュニティは、暴力犯罪や詐欺などに携わる人や借金などの問題も多く、ネガティブな方向に人を追い込むところがあると思います」
大麻から合法なアルコールに変えて体調悪化した人も
子供の頃から逆境的な環境に置かれ、発達障害や精神疾患などで生きづらさを抱えているとしても、大麻でなく他の手段でそれを緩和する方法もあるのではないかという疑問が湧く。
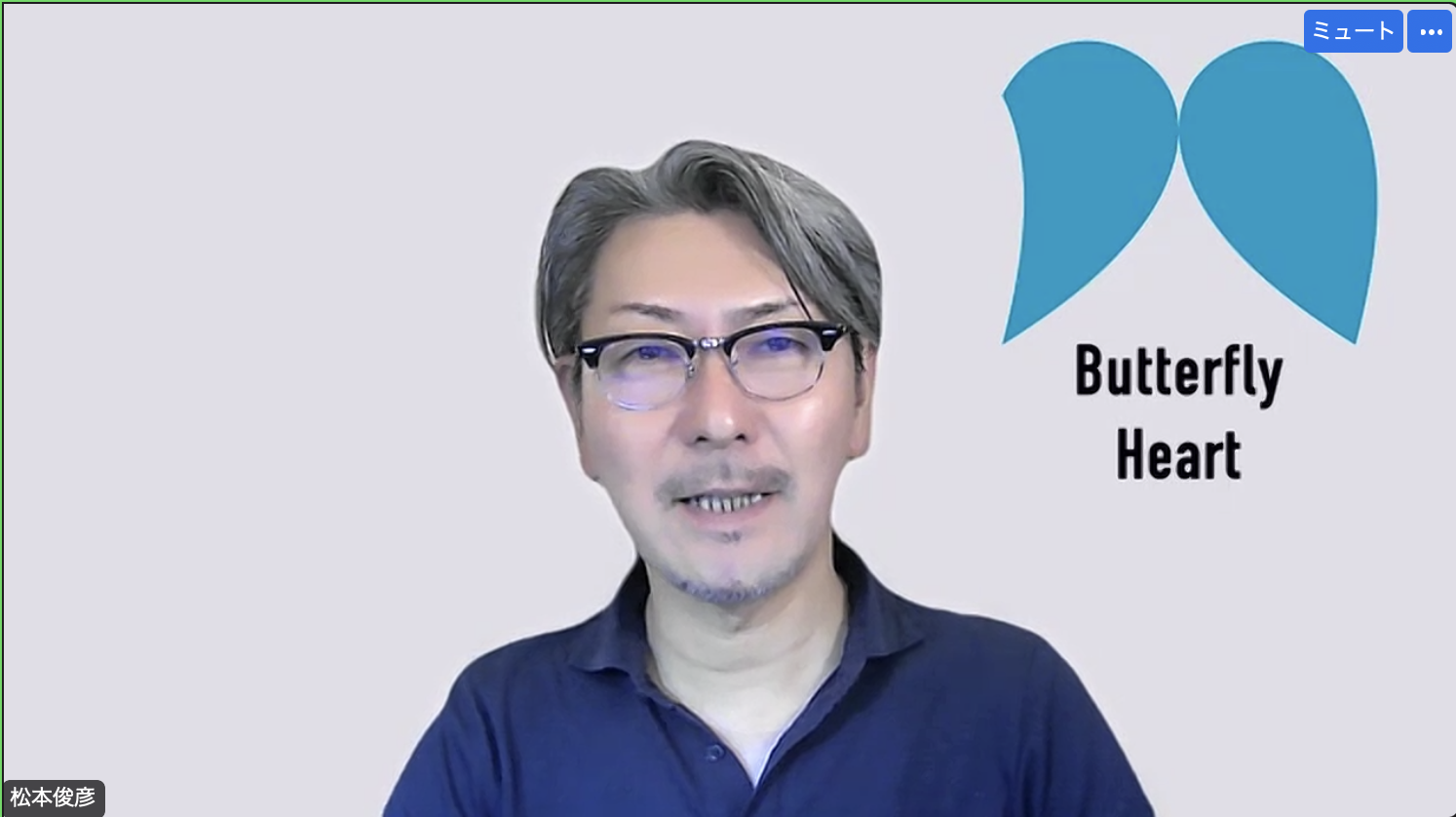
これについて松本さんは、分析対象となった参加者に似た患者をたくさん診察した経験から、こう語る。
「いろんな生きづらさがあって、精神科に行っていろんなお薬を試したが全然良くならない。トラウマがある人の中にはカウンセラーと関係がこじれて、余計傷つきが深まる人もいます。そこで、大麻を使ってみたら副作用も少ないし、ベストとは言えないかもしれないけど、これまで受けてきたサービスの中ではマシと使い続けている人はいる。探せば他の選択肢があるのかもしれないけど、アクセスしやすい選択肢の中では、大麻が1番マシだったということでしかない」
また、大麻から、アルコールなどの合法薬物に変えたことで、逆に体調が悪くなった例も経験している。
「長いこと寝る前に大麻を一服して安眠し、ちゃんと仕事もしていたのに、たまたま捕まって大麻が使えなくなった患者がいます。大麻がないとなかなか眠れないから晩酌を始めると、肝機能など内臓の状態は悪くなった。社会的には大麻を使うことはリスクですが、医学的に見てどちらがより良き人生なのでしょうか?」
「長期的に使って、害が出る人も出ない人もいて、これはお酒でもタバコでも同じです。大麻を他の嗜好品と明らかに違うものだと位置付ける根拠はあんまり見当たらない。お酒やタバコと同じように害もあるよね、というニュートラルな言い方しかできないと思います」
正高さんもこう語る。
「多くの人は、大麻は『悪』で、取り締まっている方が『善』であるという二元論の価値観を採用しています。でも、自分の人生を少しでも良くしようと考えて色々試してみた結果、大麻によって救われて、それを自分の心の杖のように使っている人がいます。世間の善悪の価値観に当てはまらないこういう軸もあるということを可視化したのがこの研究です。多くの人に伝わればいいなと思います」
