市販薬乱用、見えざる貧困 「助けて」と言えない女性を支援する現場から
ことし2025年8月、東京・世田谷区に15〜24歳の若年女性の居場所としてオープンした「ゆうカフェ」(下北沢)。同区は、「既存の行政支援ではカバーできなかった、若年女性の孤立感や悩みを解消する場にしたい」と、これまで数多くの途上国の女性支援に注力してきた国際NGOプラン・インターナショナルとタッグを組み、本事業をスタートした。
本稿では、同法人の職員として「ゆうカフェ」で相談員を務める、社会福祉士・濱田真奈さんに取材を実施。利用者が直面する“見えざる貧困”と、近年、メンタルヘルス界隈が重視する「相談」と「ケア」の関係について話を伺った。
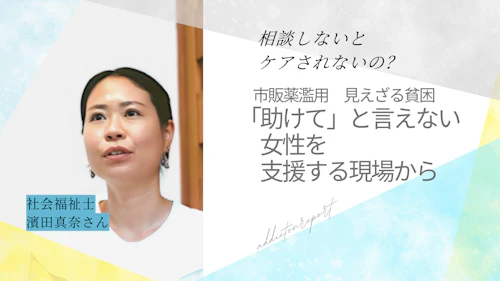
公開日:2025/09/12 09:00
(取材・文:遠山怜)
下北沢から徒歩5分、地域に開かれた「ゆうカフェ」
.png)
.jpg)
.jpg)
ーー(筆者)「ゆうカフェ」は通りに面した二階建ての一軒家で、とても開放感がありますね。駅近なのに、まるで郊外のおしゃれなカフェに来たようです。

濱田さん:地域の協働スペースとして複数団体が利用している場所を、毎週木曜・金曜の午後1時〜7時の間お借りしています(祝日・年末年始を除く。詳細は公式Xで随時更新)。開所日は、1階のホールとカフェスペース、2階のキッチンを使わせていただいてます。
現在、2名のソーシャルワーカーが常駐し、金曜日は助産師、第四金曜日には臨床心理士も在籍します。居住地を問わず、中学卒業後の15〜24歳の女性であれば、初回登録後は自由に利用できます。
なお、「ゆうカフェ」に先駆けて東京・豊島区にオープンした「わたカフェ」(池袋)では、2024年時点で月平均利用延べ人数は149人、リピート率は約60.4%となっています。利用者の主な年齢は18歳〜19歳で、高校卒業、大学入学時など環境が大きく変わった時期に来所するパターンが多いですね。利用者の半数が相談を希望し、もう半数は一人で静かに休みたい、スタッフと喋りたいなど、利用用途はさまざまです。

.jpg)
時間の使い方は自由 気軽な休憩所としても
ーー(筆者)皆さん、ここでどんな風に過ごしていますか?どういった経緯でここを知ったのでしょう。
濱田さん:自分で調べて来る方もいれば、行政の窓口から紹介されたという方もいます。過ごし方はさまざまで、スタッフとおしゃべりしたり、スマホを充電しながら休憩したり。軽食を食べに来たり、週1回の生活応援品を受け取りに来る方もいます。


ーー生理用品の無料配布はありがたいですよね。最新の高機能な製品は意外と値が張り、毎月の出費となるとかなりの負担です。使いたい製品があっても、安価で投げ売りされている商品で我慢している人も多いのでは。
濱田さん:そうなんです。生理用品はとても人気で、以前はティッシュで代用していた方もいました。うちには、いわゆる低所得世帯出身の子だけでなく、家庭に経済的な余裕があるのに、本人だけが困窮しているケースの方もいます。両親は共働きで住む家はあるけれど、食費や衣服、生活費や医療費は全部自分持ち。受験や進路選択で親の期待に応えられなかったことから、家庭内で冷遇されている例もあります。
こうした状況下にいる人は、行政支援の要件に当てはまらないことが多く、生活保護も扶養能力のある家族がいて、世帯収入があると申請が下りません。一応、生活が成り立っていて目立った暴力もないとなると、児童相談所も介入できない。
また、家庭環境の問題もあってか、本人が精神疾患を患っていたり生まれつき発達障害があったりして、体調も万全ではなく、バイトも休みがちで生活が困窮しているケースも多いです。
ーーパッと見は普通の家族に見えても、親子間の精神的・経済的なサポートが十分でなく、“見えざる貧困”に置かれている若者は少なくないと。
濱田さん:そう思います。私は以前、児童養護施設の職員として働き、虐待している親御さんと何度か直接話したことがあります。彼らは決して、一般的に想像されるような、愛情が欠落し悪意に満ち溢れた人物ではないんですね。なんだったら、子どもに愛情はあるし支えてあげたい思いはあるのに、できない。
仕事は多忙なのに家計は苦しく、配偶者は子育てに無関心。おまけに親の介護や子どもの育てにくさなど、いろんな要因が重なって、力尽きてしまう。日本は「最低限の生活水準を満たしている」子育て家庭への支援が乏しく、親のリソースが限界を迎えていても、「自分で産んだのだから」と自己責任にされてしまう。
社会から母親・父親はこうあるべきと期待される一方で、誰もどうすれば子どもを愛せるのか、どう頑張れば愛し続けられるのか教えてくれない。我が子をかわいいと思うことと、子どもの成長を通じて変わらず愛し続けることは、必ずしもイコールではないのに。
ーー社会が「親の愛」に期待するところは大きいですよね。家庭内トラブルは、「お母さんなんだから」と愛情でなんとかするよう求められる。親のリソースを使い果たした結果、そのツケが子どもに回ってくる。

濱田さん:利用者さんと話していると、話を聞いてくれる人を求めているのだなと感じます。皆さん、性格も家庭環境もバラバラなのですが、総じて人との接点が少ないように思います。両親が揃っていても、生活にいっぱいいっぱいで子どもの内面に目を向ける余裕がない。
親子間で十分に関係性が構築されていない分、他人との距離感に悩む方は多いですね。困っていることがあっても、友人や知人にどこまで頼っていいのか、相手の迷惑になってしまうのではないかと逡巡してしまう。相手にどこまで伝えてよいのか伏せるべきなのかを、とっさに判断できない。
他人との境界線をどこで引いたらよいかわからず、ひとりで抱え込んでしまったり、相手に接近しすぎて関係が壊れてしまったり。相手と程よい距離感で付き合うことができなくて、極端な方向に行きがちです。
そうした経験もあってか、人付き合いに慎重になっている利用者さんは多いと思います。表向きは陽気でおしゃべりだったり、人と難なく接することができたりする子も、相手が信頼に値する人物なのか常に探っていたりします。ですから支援者も、相手が怖がっている、警戒していることを前提に接する必要があると思います。
ーーこうした場所につながってくれた人でも、そう簡単に悩みを話したり、核心を打ち明けたりはしないということですね。話をする中で、どんなことに気をつけていますか。
濱田さん:まず第一には、無害でいることですね。その人の価値観を否定したり、考え方を無理に変えようとしないこと。支援者の『良かれと思って』が、本人の自己決定権を侵害することにもつながりますから。本人の気持ちをなるべくそのまま受け止めるよう心がけています。
たとえば、利用者さんの中には、市販薬の過剰摂取(オーバードーズ)や自傷行為をしている方もいます。それを聞いても、こちらからむやみに『そんな危ないことはやめて』とは言わないようにしています。もちろん、オーバードーズも自傷行為も心身に大きな負荷をかける行為だけれども、それをすることで本人が今、生きていられるのも事実です。他につらい気持ちを緩和できそうな対処法はないか一緒に探して、次回、別の対処方法を試してみてどうだったか教えてもらったり。
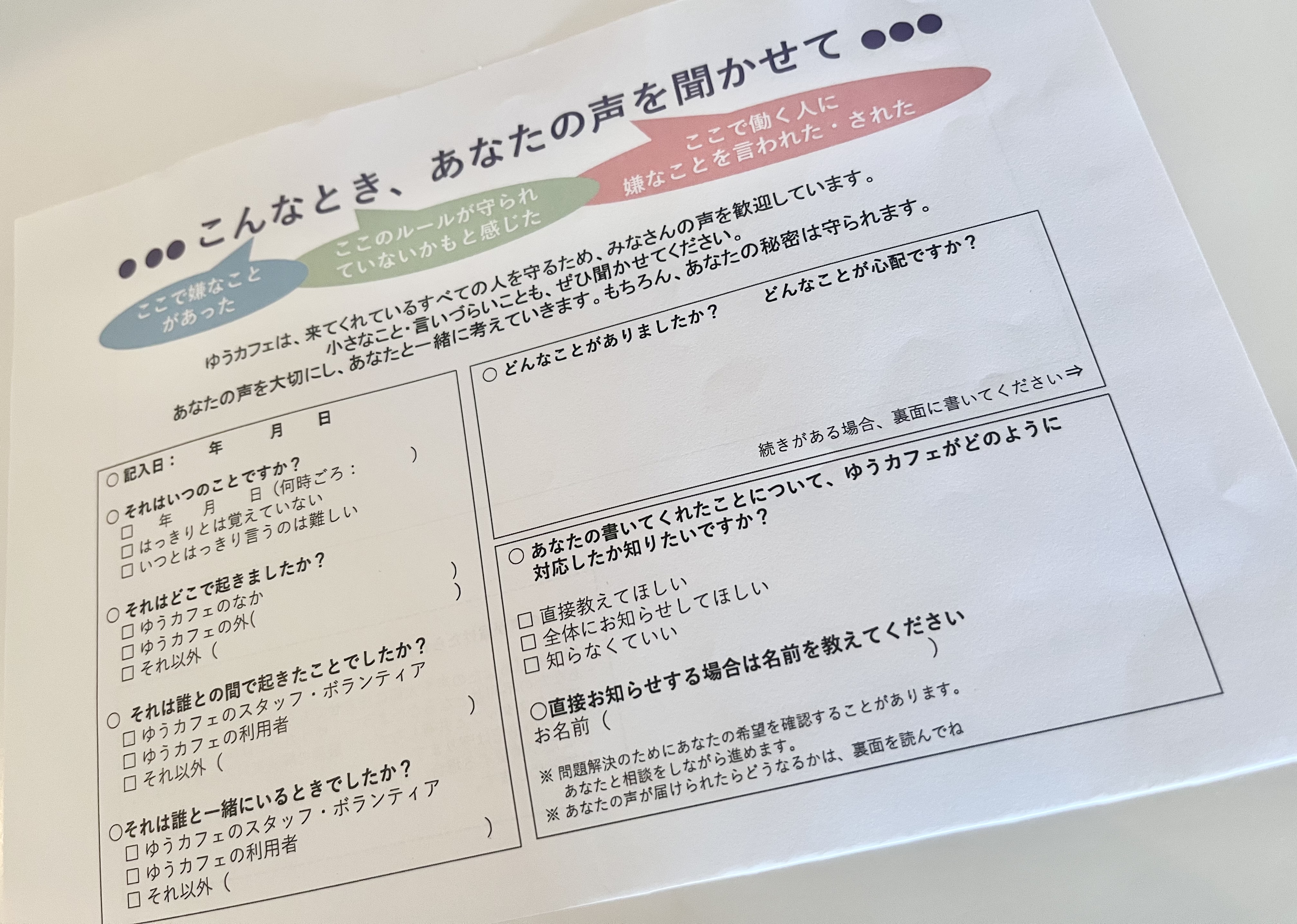
とはいえ、中には危険性の高い自傷行為を繰り返している人もいます。特に、トラウマを抱えている人の場合、相談機関のような安心できる場にいるときこそ、過去の嫌な出来事の記憶が再燃しやすいと思います。危機的状況下では、常に厳戒態勢でいるから過去を振り返る余裕がない。安全な場所で気が緩んだときに、今まで押し殺していたものが一気に出てくる。過去のつらかった出来事を無意識のうちに再現することで、苦しい記憶に対処しようとする側面もあるのではないでしょうか。
そうした場合は、死にたいぐらいつらい気持ちを受け止めつつも、『せめて今日はやめてみない?』と提案することもあります。心配しているし、生きてまた会いたいと、こちらの思いは伝えるようにしています。心が疲れているとき、他人のちょっとしたアドバイスが、自分を否定しているように感じることがあると思うんです。特に、「ゆうカフェ」のような開かれた支援の場では、相手が『この人と話すのしんどいかも』と思ったら、そこで関係が終わってしまう。学校や職場の人間関係のように、言い過ぎてしまったから次に会ったときにフォローしようなんてできない。一回一回が大事で、無理に相手を変えようとせず、つながり続けられる関係でいることを目指しています。
よく、精神的な安定と自立のために依存先をたくさん持とうと言われますが、いろんな課題を抱えている人にとって、人間関係を増やすのはすごく難しいと思います。かろうじてある細いつながりだって、いつどんな出来事で途切れてしまうかわからない。支援者としては、まず、今あるつながりを途切れさせないよう、心がける必要があると思います。
ーー相談できる場につながったからといって、すぐに問題解決に向けて話が進むわけではないんですよね。本人が安心できて、一歩踏み出したいと思える関係性があってこそ、その先の選択肢が見えてくる。
濱田さん:相談機関の一番の特徴は、支援の見通しを常に更新し続けることにあると思います。たとえば、児童養護施設で子どもを保護した場合、担当職員は本人の生育歴や家族構成、過去の受診履歴など、重要事項を事前に把握することができます。それらの情報を照らし合わせて、施設で今後どう生活していくか、詳細な見通しと綿密な計画を立てることができる。
一方、相談機関では、利用者さんの生活状況を事前に知る手立てはありません。本人から家庭環境や日々の生活の話を聞くことはできるけど、表だって言わないこと、第三者に軽々しく言えないことはたくさんあるはず。なので、何気ない会話を手掛かりに、その人が普段どんな家庭でどう生活しているのか、ちょっとずつ理解して、支援を見立て直していく必要があります。たとえば、『短いスカート履きたいけど彼氏に怒られるんだよね』みたいな話だったら、もしかするとパートナーがすごく支配的なのかもしれない。本人はデートDVに関する知識はあるのかな?もし興味がありそうなら、区のデートDV防止講座を紹介してみるのはどうだろう、とその都度、支援の照準を合わせていくイメージです。
本人を理解するための大事な手がかりって、ふとした瞬間に口をついて出るものだと思います。たとえば、高校生の子が『今日は体がだるい』と話しているとき、『深夜2時帰りはキツいよね』とポロッと愚痴を漏らしたり。聞いている側からしたら、帰宅時間が深夜2時だとして、日中はどうしているのだろう。それで学校は通えているの?どうしてその時間でないと帰れないのだろう?と疑問が次々浮かんでくる。
でもそこで『え!深夜2時?どうしたの?何かあったの?』とこっちが大袈裟に驚くと、本人は警戒して口を閉ざしてしまうので、『そうなんだ。その日は何してたの?』と、あくまでその子の日常生活に興味を持って、話を聞きますね。何気ない雑談が続く中で、またどこかで大事な情報が得られるかもしれない。その人が口にした断片的な情報をつなぎあわせると、本人が置かれている環境が見えてくる。ちょっとずつ理解しては修正してを繰り返す中で、支援の方向性が見えてきたりします。支援者にとって、『相談に至るまで』が最初のハードルだと思います。
ーー若者の自殺や市販薬の過剰摂取を予防する政府広報では、「相談して」と当事者に援助希求行動を促すメッセージが多用されています。しかし国や行政が、相談する手前のSOSを拾い、受け止めるために、やるべきことはまだまだたくさんあると思います。
濱田さん:行政の相談窓口の対応ひとつ取っても、改善すべき点は多いと思います。たとえば、利用者さんが相談窓口で窮状を訴えても、申請要件に合致する制度がなければ、『うちで提供できる支援はありません』と素っ気なく断られて、話が終わってしまう。もちろん、行政としては、業務として申請要件を満たすか判断したにすぎないでしょう。でも、利用者側からしたら、ずっとひとりで耐えてきて、もうどうしようもなくなって、最後の切り札として助けを求めにきているのだと思います。
仮に、目当ての支援が使えなかったとしても、他に利用できそうな制度はないのか、相談に乗ってくれそうな民間団体はないのか、本人の話を聞きながら一緒に探すことはできると思うんです。それもせずに、『うちでは無理です』の一言で断られたら、その人はもう二度と行政や公的機関を頼ろうとは思わないでしょう。
相談が必要な人ほど、相談することで傷つけられ、裏切られてきた過去がある。当事者に『相談しましょう』と呼びかけたところで、『いやいや、その前にあなたは私になにをしてくれるの?まず手のうちを見せてよ』となるのは、当然ではないでしょうか。
あとは、保護要件の見直しも必要だと思います。たとえば、あるDVシェルターでは、職員から中〜重度の身体的暴力被害が認められないと施設を利用できないと言われたこともあります。要は、顔や体がボコボコにされてないと保護できないと。その施設で緊急避難が認められる条件が、「命に関わる危険が迫っている」ことにあるからだと思いますが、それではほとんどの人が対象外になってしまう。まさに殺される寸前で命からがらDVシェルターにたどり着ける人は、はたしてどれくらいいるのでしょうか。
また、ほとんどの暴力被害者は、身体的暴力よりも恫喝や暴言などの精神的暴力や性的搾取、経済的制裁など、パッと見で第三者がそれとわからないような被害を受けています。こうした人たちはそもそも保護されないのです。地域によって相談してもケアされない人がたくさんいる現状を、変えていくべきではないでしょうか。
ーーそうした人の存在に気付き何かしてあげたいと思う人に向けて、アドバイスはありますか。

濱田:負担にならないようであれば、本人の話を聞いてあげてほしいと思います。でも、自分ひとりで支えるのはちょっとしんどいと思ったら、無理せず自分を大事にしてほしい。その人が使えそうな民間団体や相談機関を調べて、『こんなところがあるよ』と知らせるだけでも十分だと思います。自分が苦しくならない範囲で、できることをしてもらえたらと思います。
