貧困と暴力、薬物に苦しむ3世代の物語『ヒルビリー・エレジー −郷愁の哀歌−』#依存症を描いたおすすめ映画五選(第五夜)
副大統領に就任予定のJ・D・ヴァンスの回想録をロン・ハワード監督が映画化。
イェール大学ロースクールに通う青年は、突然の連絡を受けてオハイオの田舎に帰郷。そこはグローバル時代のアメリカから取り残された工業都市。貧困にあえぐ人たちの家庭では暴力がはびこり、ドラッグが蔓延していた……。

公開日:2025/01/04 08:00
2025年1月に発足する第2次トランプ政権の副大統領に就任予定のJ・D・ヴァンス。最近もニュースでその姿を目にした人も少なくないだろう。
彼が政界に出る前の2016年、当時まだ無名の作家に等しいヴァンスが書いた回想録『ヒルビリー・エレジー アメリカの繁栄から取り残された白人たち』は全米でベストセラーとなった。
「ラストベルト(さびついた工業地帯)」と呼ばれる地域のオハイオ州ミドルタウンと、アパラチア山脈の町、ケンタッキー州ジャクソンで育ったヴァンス。
地元の高校卒業後、海兵隊に入隊、イラクに派兵される。除隊後、オハイオ州立大学、そしてアイビーリーグの名門イェール大学ロースクールを卒業……。
そうした半生を映画化したものが『ヒルビリー・エレジー -郷愁の哀歌-』(2020年Netflix配信)である。
監督は『ビューティフル・マインド』『ダ・ヴィンチ・コード』などでヒットを飛ばしてきたロン・ハワードだ。
※ネタバレを含みますのでご注意ください
(文・青山ゆみこ)
●取り残された地方の白人労働者階層「ヒルビリー」
タイトルにある「ヒルビリー」、そして原作の書名に添えられた「アメリカの繁栄から取り残された白人たち」について、少し補足説明が必要かもしれない。
ヴァンスは白人だが、アメリカ北東部のいわゆるWASP(ワスプ/ホワイト・アングロサクソン・プロテスタント)ではない。
自身を「スコッツ=アイリッシュ(アイルランド島北東部からアメリカに移住してきた人々)」の家系に属し、「労働者階層の一員」として働く白人アメリカ人のひとりだと見なしている。
彼はこう語る。
そうした人たちにとって、貧困は、代々伝わる伝統といえる。先祖は南部の奴隷経済時代に日雇い労働者として働き、その後はシェアクロッパー(物納小作人)、続いて炭鉱労働者になった。近年では、機械工や工場労働者として生計を立てている。
アメリカ社会では、彼らは「ヒルビリー(田舎者)」「レッドネック(首筋が赤く日焼けした白人労働者)」「ホワイト・トラッシュ(白いゴミ)」と呼ばれている。
だが私にとって、彼らは隣人であり、友人であり、家族である。
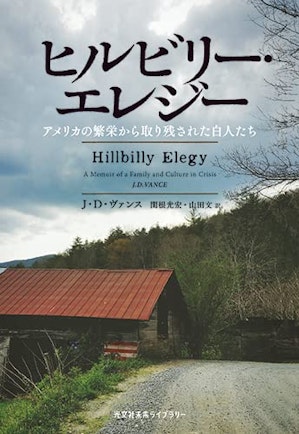
「ヒルビリー」は「田舎者」の蔑称である。
グローバル時代のアメリカから取り残された工業都市出身の田舎者として、自身を「ヒルビリー」と称するヴァンス。そこには簡単には言い表せない、故郷への複雑な思い、そして自分のルーツに対する誇りのようなものが含まれている。
●薬物依存症に苦しんできた母
名門イェール大学ロースクールの学生となったJ.Dヴァンス(ガブリエル・バッソ) が、夏のインターンに採用されるチャンスを前にしたシーンから映画は始まる。
経済的に困窮している学生として「学費を払う」という切実な目的であり、夢に描いていたキャリア実現の最初の一歩となることを、彼は自覚している。自分は今、非常に重要な岐路にいるのだと。
そこに故郷の姉から一本の電話が入る。「母親が薬物の過剰摂取で運ばれた」と。
強いショックを受けつつも、青天の霹靂というわけでもなさそうに、すっと現実を受け入れるヴァンスの様子から、これが初めての出来事ではないことが気配として伝わってくる。
母親ベヴ (エイミー・アダムス)は、若い頃から薬物依存症に苦しんできた。
この作品は、自分の将来を左右する面接時間までのタイムリミットが迫るなか、ヴァンスが故郷に戻り、姉のリンジーとともに母を助けるために奔走するという展開が軸になっていて、「はたして間に合うのか」というドキドキサスペンスのようで、初っ端から目が離せない。
●それぞれの生育環境
故郷ミドルタウンは、アパラチア地方の一つ、鉄鋼メーカーの本拠地として知られるオハイオ州南部の地方都市。「ヒルビリーの街」だ。
他の製造業と同様に急速に衰退していった街は荒廃し、失業者があふれ、貧困にあえぐ人たちの家庭では暴力がはびこり、ドラッグも蔓延している。
ヴァンスはそんな街の貧しい家庭で幼少期を過ごした。
物心ついたときには両親はすでに離婚していて、母は看護師をしながらなんとか二人の子どもを育てていた。高校時代は成績優秀だった母だが、卒業後に妊娠し、大学への進学は叶わなかった。
若いベブはシングルマザーとして懸命に幼い子どもを育てつつ、寂しさからなのか恋人をつくっては別れを繰り返していた。
彼女は感情のコントロールが苦手で、キレるととんでもなく暴力的な面を見せる。しかし冷静になるとひどく自分を責めて落ち込んで、精神的に不安定な面を抱える自分に対して苦しんでいる。
なぜ、どうして、と。

看護師である彼女の職場にはごく当たり前に鎮痛剤などの薬物があった。いつしかベブはルールを違反して薬物を入手し、自分のために使用するようになる。時には勤務中にハイになり職場を解雇され、ついには看護師資格を失ってしまう。
やめたい。だけど、やめられない。どうすればいいのかわからない。
思うようにいかない自分自身に対するもどかしさ、人生のどうにもならなさへの苛立ちのようなものが、彼女を薬物に走らせるようにも見える。
その理由は複合的だろうが、彼女の生育環境にも一端があることが、次第に明らかになっていく。
そんな母とヴァンスの生い立ちに深く関わっているのが、祖父母の存在だ。
彼の味方でいてくれた祖母ママウ(グレン・クローズ)と母は、いつも反発し合って強い確執が垣間見える。
一家の年長者として振る舞う祖母だが、実は彼女には13歳で妊娠し、故郷を捨てたという過去がある。
幼い頃のヴァンスにはわからなかったが、いつもやさしかった祖父が、かつてひどいアルコール依存症者として家庭をめちゃくちゃにし、子どもの母にひどいトラウマ体験を与えた存在であったことも回想シーンで描かれている。
祖母、母がそれぞれもつ「人生のつまずき」のような断片に触れるたび、言葉を失いそうになる。
●「手を切る」必要と、「手を握る」決断。
世代間の負の連鎖なんて言葉にまとめられないような、一人ひとりの感情が連続して彼らは生きていることが画面を通して伝わってくるのだが、同時に圧倒的に彼らに「言葉がない」ことも印象的だ。
大切に思う家族に対して「アイラブユー」など「大きな愛」の表現はできても、繊細な心の機微を表現するすべをもたない。不機嫌に黙り込むか、感情にまかせてののしりの言葉をぶつけてしまってばかりだ。
愛情の度合いとは別で、そんな場=家庭は荒れる。
母ベブは、迷いや不安などネガティブな感情のほとんどを、暴力的な行動で表現してしまう。痛みや恐怖が、また暴力を生む。あるいはしんどい気持ちを麻痺させるために、薬物が使用される……。
うまくやっていきたいのに、思えば思うほど、ままならなさが自分を破滅的な行動へと駆り立てる。
ヴァンスがそこから抜けだすきっかけとなったのは、一時的な「母との別れ」だった。
問題のあるパートナーを選びがちな母に連れ添って、住居も転々と暮らすうちに、彼はよくない環境に慣れていって、当たり前に酒や大麻に手を出したり、ほとんど犯罪行為にも手を染めていったりするようになっていた。
そんな少年を文字通り命がけで引き留めたのが、祖母ママウだった。
助けを出す祖母、その手を握った孫。
持病を抱えながら、食糧配給を受けるような余裕のない生活だったが、少年ヴァンスは初めてそこで安定した環境に身を置くことができたともいえる。
祖母の庇護により、精神的にも環境的にも初めて勉強に身を入れることができるようになり、ヴァンスは自分が変わる一歩を踏み出していく。
彼自身もわかっている。自分が生まれ育った故郷から抜けだす方法は限られていることを。勉強して良い教育を受けることが、その数少ない選択の一つだと。
少し話がずれるが、回顧録『エデュケーション』の著者、タラ・ウェストーバーのことも思い出した。
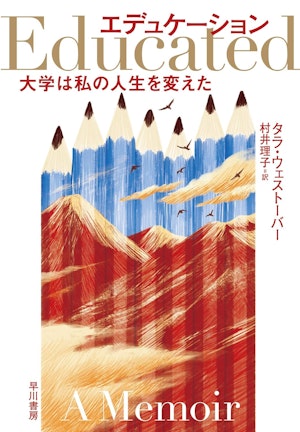
アイダホ州に生まれ、両親が病院、公立学校、連邦政府を頼らないサバイバリストだったため、自宅で助産師の手を借りて生まれたタラは、9歳まで出生届が提出されていなかった。そのため学校にも行かせてもらえなかった。
大学に進学した兄の影響を受け、10代半ばに独学で大学資格試験に合格。のちにハーバード大学で研究員となったその半生は驚きの連続で、この回顧録は全世界800万部を突破するベストセラーとなった。
タラの人生の転機にも、必ず人との出会いがある。彼女に手を差し伸べる人の手を掴んで、タラも人生を変えてきたのだ。
●家族の話を語りはじめるヴァンス
映画『ヒルビリー・エレジー』は、ヴァンスが故郷に帰るところから物語が始まるということが印象的だ。「故郷を捨てる」という言葉があるが、ホームはそう簡単に捨てられない。
縁を断ち切る方がいい場合もある。あくまで本人の選択が可能であることが重要に思う。
ヴァンスはこれからの人生を生きるために、「母を捨てない」という選択をする。母のベブも諦めない。彼女と一緒に回復を目指して頑張ろうと。これまで幾度も裏切られてきた彼にはけして簡単ではない決断への葛藤が、この一本の映画に凝縮されている。
もちろん家族だけでは難しいことをヴァンスは知っている。だから人を頼る。その難しさも切実に描かれている。
さて、いったいなぜヴァンスは原作となる回顧録を書いたのか。
それは、母、祖母世代という家族三世代が「ヒルビリー」として生きてきた家族史を語ることが、必要だったからではないだろうか。
映画の終盤、それまで「人に話すのが怖かった」という家族の物語を、ヴァンスが心から信頼する人に「語りはじめる」場面がある。
せきをきったように言葉があふれ出す彼と、その言葉から目を逸らさず、真正面から受けとる人の姿を見ていると、なぜだろう、わたしの心まで解放されるような「自由」を感じた。
それぞれの世代、家族の一人ひとりの人生に葛藤があり、個人だけではどうしようもない「時代の流れ」もあった。絡み合った困りごとを抱える家族の問題は複雑すぎて簡単には紐解けない。
時間を遡り、故郷の歴史を、自分たちのルーツを語ることからしか始まらないのかもしれない。
アメリカの話ではあるが、日本でも同じような状況はないだろうか。連鎖するように受け継がれる貧困から抜けだすことの難しさ。
でも、希望もあるってことをこの作品が教えてくれる気もするのだ。

改めて、祖母を演じるグレン・クローズがすごい。というかすさまじい。今から37年前、『危険な情事』(1987)ではマイケル・ダグラスとの共演で、不倫相手を執拗に追い詰めるストーカーを演じたあの大女優だ。
だぶだぶのTシャツを着たがらっぱちのおばあちゃんの姿を見た瞬間、そんなことを忘れてしまうほどの熱演が圧巻。衝撃の名演である。
笑いながら泣いているような瞳が忘れられないエイミー・アダムス。薬物をやめたいのに、やめられない。依存症の悲しさを深く突きつけてくる熱演は、胸が痛んで息が止まりそうになるほど、切ない。
また、エンドロール間際に映し出されるリアルなヴァンスの家族の写真を目にすると、驚いて思わず「え!」と声が出る人が多いはず。グレン・クローズもエイミー・アダムスも、一瞬見分けがつかないほどそっくりなんだもん(すごすぎる)。
画面にそっと添えられる「母のその後」にはほっと胸をなで下ろすような「希望」が詰まっている。
「ヒルビリー」の家族史は、ある意味アメリカ近代史ともいえるだろう。
ヴァンスが政治家となるずっと前の話なので政治色は無縁だが、現在の彼を知るヒントがあるかもしれない。
でもそれ以上に「ヒルビリーの家族」の物語を聞き入って、その余韻がいつまでも胸に残る作品だ。
※Netflix映画『ヒルビリー・エレジー -郷愁の哀歌-』独占配信中
※ 「たかりこチャンネル」でも紹介されています。ぜひ、こちらもご覧ください。
