市販薬の乱用問題、ドラッグストアで孤独・孤立対策 NPOとの連携で新たな道を開く 〜ツルハホールディングス
若年層の市販薬の過量服薬(オーバードーズ、OD)が社会問題になっている中で、ドラッグストア大手のツルハホールディングス(北海道札幌市東区)は、乱用の背景にある「孤独・孤立対策」として独自の取り組みを進めている。

公開日:2025/10/23 02:00
若年層の市販薬の過量服薬(オーバードーズ、OD)が社会問題になっている。救急搬送されたり、場合によっては死につながる問題だ。ドラッグストア大手のツルハホールディングス(北海道札幌市東区)は、乱用の背景にある「孤独・孤立対策」として独自の取り組みを進めている。市販薬の乱用問題に一石を投じる。孤独孤立の問題でのチャット相談をしているNPO法人「あなたのいばしょ」(東京都千代田区)と連携し、相談窓口を紹介するポスターを店舗に掲示する試みを始めた。ドラッグストアに来店した人たちに専用の相談窓口を設置したのは異例の試みだ。
このプロジェクトの発案者である立石大介さん(グループ調剤戦略部部長)に話を聞いた。
「薬剤師としての個人的な経験としては、あるアルコール依存症の患者さんとの出会いが印象深いです。ある日、血まみれで来店されたんです。『どうされたんですか?』と聞くと、『血反吐を吐きながらでも酒を飲まないと、気が済まない』と泣き崩れたんです。同時に『助けてくれ』とも言われました。そのとき、『助けるって何だろう』って考えました。何を言っても止められないんです。
その方は結局、AA(アルコホーリック・アノニマス、アルコール依存症のひとたちの自助グループ)につながったんです。こちらは患者さんにアプローチをしますが、拒絶される場合が多いです。一方、その患者さんのように受け入れてくれる場合もあります。そうした患者さんとはあまり出会いがありません。巡り合わせです。薬剤師が行う、従来の情報提供や服薬指導、モニタリングは、乱用者にとっては無意味です。わかってやっていますから。薬をちゃんと飲ませる前提の仕事ですが、意図的に問題を起こす人には通用しないんです」

個人的な経験からドラッグストアでの対策を発案
こうした薬剤師としての経験から、無力感が生じた立石さん。そんな客を拒絶するのではなく、手を差し伸べる方法を探求した。その結果、薬物乱用対策として「孤独・孤立対策」の取り組みを思いついた。社会問題になっている若年層の市販薬のODの問題へのアプローチの一つとして捉えている。
「全国の精神科医療施設における薬物関連精神疾患の実態調査」によると、2010年以降、処方薬の乱用患者が増加した。22年の調査では過去1年以内に薬物使用が見られる薬物関連障害患者の半数が処方薬と市販薬を乱用している。その結果、自損行為による救急搬送も増えている。そのうち、23年の10万人あたりの搬送人員は20〜39歳で67.4人。19年の51.0人と比べると約16人増えている。また、0〜19歳の場合は23年では27.6人だが、19年の15.6人と比べて12人増加した。
そんな中で、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」(薬機法)が改正された。未成年者に対して、「指定乱用防止医薬品」の大容量包装や複数個の販売を禁止した。一方、小容量製品の販売の場合には年齢確認をし、薬剤師か登録販売者が対面で販売することになる。また、インターネット等の通信販売で「指定乱用防止医薬品」を販売する時には、若年層や18歳以上の大容量製品の多量購入者に対し、テレビ電話等で「対話式」で確認することが義務化され、26年5月までに施行される。
「プロジェクト発案の出発点としては、(市販薬のOD等)社会的にいろいろと問題が取り沙汰されていることもそうですし、法律が変わることが議論されていることもありました。ドラッグストアや調剤薬局の現場を経験した身としては、自分たちでもどうすることもできないこともあります。(ODしそうな客に市販薬を売ることを)断ることはできるんですけど、なんら問題の解決にならない。それに断ったとしたら、その人たちはその後どうするのか。ただ、『自分たちが問題から免れた』とか、『自分たちは(お客さんを)守ったからOK』みたいになるのはどうもしっくりこない。そのため、自分たちができることは何かを考えたんです。文献を漁ったり、学問的な研究成果を調べたりしました」
ドラッグストア内に支援先を紹介するポスターを掲示
そんな中で、薬物依存の患者を診ている、精神科医の松本俊彦さんが発信する内容に辿り着いた。
「松本先生は、ドラッグストアの店舗数が増えたことが、市販薬に依存する若者たちが増えたことの根源の一つである、とおっしゃっていました。しかし、ODをする若年層の人たちを拒絶することではなく、なにかしら手を差し伸べる方法があるのではないか、という話がありました。そのため、ドラッグストアの店舗内に『ダメ。ゼッタイ。』のポスターではなく、支援先を紹介するポスターを掲示すべきではないか、という話がありました。それを知ったとき、実際にやってみようじゃないかと思ったんです」

しかし、会社だけで行うのは限界がある。相談先となるような仕組みを作ることができないと考えた。話を聞いたり、カウンセリングをしたりすることは専門的な知見や能力、そして、それらを発揮する仕組みが必要となるとも考えた。
「そうした仕組みを作ることを自分たちだけで作るのは無理だと感じていました。その中で、24年10月に日本公衆衛生学会に行ったんです。それまでにもいろんな支援団体をウォッチしていたんですが、その学会に『あなたのいばしょ』の方々がブースを構えていました。そこで、『自分たちも孤独・孤立対策をしたいが、自分たちだけではできない。協力できる、あるいは一緒にできるパートナーを探しているんです』とお願いをしたんです。幸い、先方は協力していただけるということでした」
支援団体による専用の相談窓口を設置してみたら…?
ただ、ツルハは全国に2,681店舗(25年9月30日現在)ある。このうち、調剤薬局だけだと約1,000店舗ある。全店舗にポスターを掲示した場合、どのくらい相談があるのかわからない。最悪、相談先がパンクする可能性もある。そのため、「一度、法人内で議論させてください」とのことだった。検討の結果、店舗数を限定し、専用の窓口を設置することになった。
こうした社内での企画提案は、立石さん個人のアイディアから始まった。「あなたのいばしょ」へ提案した段階ではまだ個人的な思いからだった。
「最初の段階では、私個人の提案でした。会社全体でやりたいが、パートナーがいないのに、社内で話せない。そのため、先に『パートナーになっていただけますか?』と聞いたという流れでした。つまり、社内で企画を成立させるための前段としての提案でした。その提案から約1ヶ月で『あなたのいばしょ』さんから『できます』という返事をいただきました。専用窓口としては、受ける店舗数を限定し、スモールスタートとして取り組むという話になっていったんです」
外部の協力が得られたことになるが、社内の議論はどうだったのだろうか。
「私の所属する、調剤関係の部門の長がいますが、同じ薬剤師なので理解してもらえました。『それはいいことだし、他(の同業他社)はやっていないのでいいじゃないか』と言ってもらったんです。そのあとに、社長に直接説明に行きました。『そういうことこそ、もっと胸を張ってやるべきだ』と言ってもらえました。『それをやって何の意味があるのか?』と言われるかと思ったんです。ところが、『競合がやっているからとか、宣伝になるからとかじゃなく、誰もやっていないことだし、いいことなんだから胸を張ってやったらいい』と言われました。非常にありがたいと思いました」
薬物やアディクションに限らず、誰でも相談できる形に
立石さんと「あなたのいばしょ」が出会ってから、1年以内に企画が実現したことになる。
「会社では年間スケジュールが決まっています。しかし、協力していただけるパートナーを確保した上で、社内で提案したため、他の企画より実現が早かったと思います。各地でドラッグストアを運営する責任者たちにも同じ説明をして、趣旨に賛同していただきました。決めるまでよりも、その後の準備の方が時間を取られました。店舗の選定や掲示物のデザインは、私がやりました。ホームページも自分で作りました」
仕組みとしては、店舗内のポスターにあるQRコードを読みこみ、専用の相談窓口にアクセスすることができるようにした。シンプルに設計し、薬物やアディクションに限定せず、「困ったら誰でも相談可能」とした。サービスは「孤独・孤立対策強化月間」の25年5月にスタートした
「当時、私は札幌本社勤務でした。企画提案をするまでは、薬物乱用の関係者との出会いはありませんでした。それまで、(精神障害者の活動拠点、社会福祉法人「べてるの家」がある)浦河町のオープンダイアローグ(統合失調症の治療的なアプローチ)のイベントがあり、そこで話を聞いてはいました。
そこで学んだことから、最初にポスターを掲示するとしたら、(薬物依存症からの回復を目指す人たちのためのリハビリ施設である)『北海道ダルク』の近くにしようと思ったんです。札幌本社とほぼ同じ通りにありました。薬物依存症の人たちの集まりがあること、集まることに意味があることをほとんどの人が知らない。それを社内で説明したりもしました」

相談者の約8割が「希死念慮」を訴えていた
6月15日までにQRコードの読み取りが370件、そのうち、相談へのアクセスは約40件になった。相談者の約8割が「希死念慮」を抱えていた。いのちの電話や自殺対策のSNS相談と比較しても割合が高く、一定の効果があることがわかった。
「国内の大規模な都市、例えば、札幌や福岡、京都、広島、浜松などの店舗に拡大していき、さらに全国へと展開していきました。その後も可能な限り、店舗にはポスターを掲示することをお願いした。そもそも、こうした取り組みは新しいです。
ポスターには『薬物』や『アディクション』のことは書いていない。困ったら誰でもいいという形にしています。期間中にアクセスは多くなかったのですが、相談は着実にありました。直接、ポスターからQRコードを読み取ってアクセスしなくても、自宅で検索する間接効果も期待できると思っています。9月までは『あなたのいばしょ』で専用の相談窓口を置いていました。専用チャットなら100%応答をしていました。現在では一般の相談窓口を紹介しています。
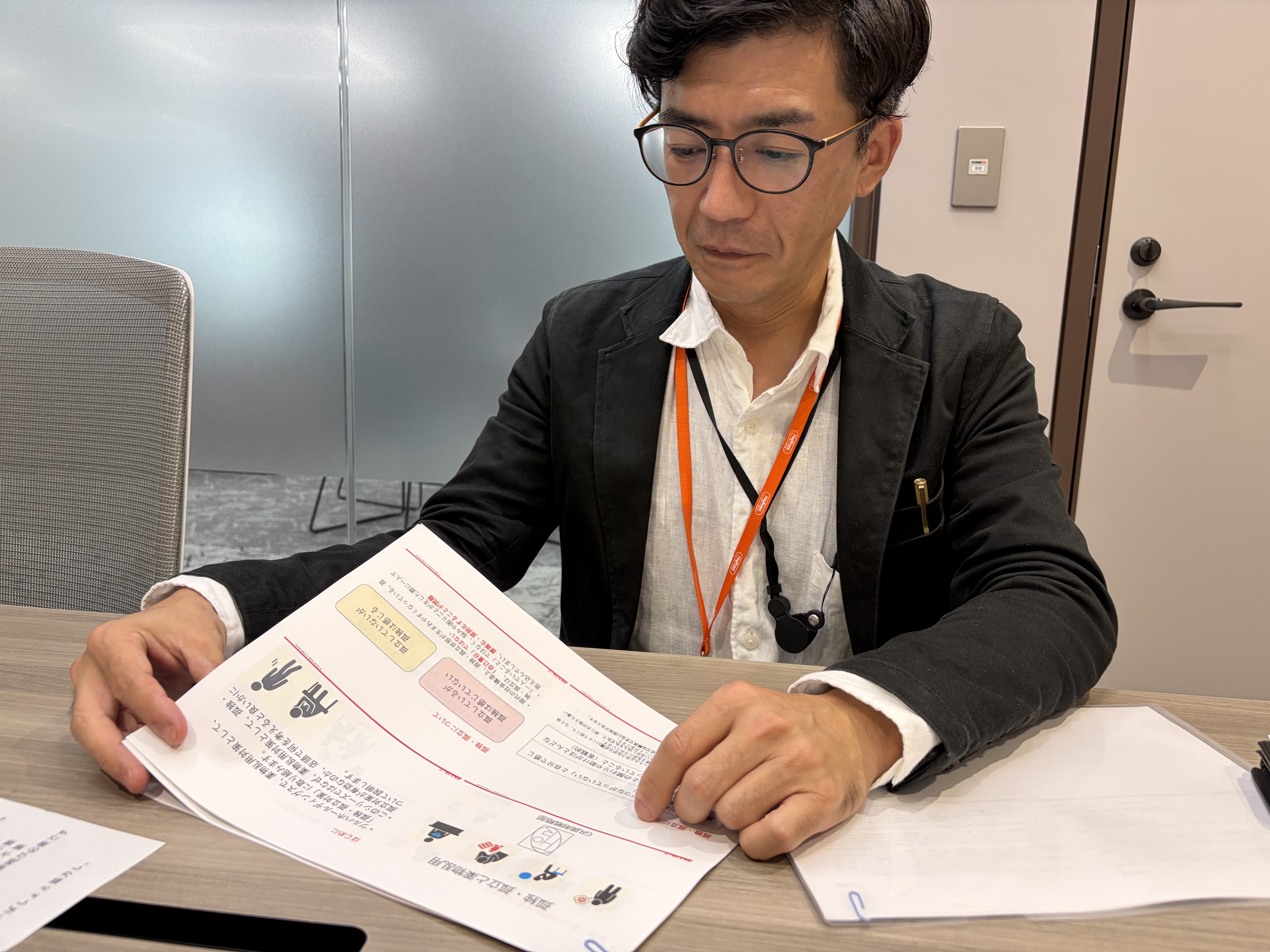
その後、松本先生には、本の出版イベントを見つけて、会いに行ったんです。ここなら直接話せると思って。そこで、『先生の言うとおりのことをやってみて、うまくいったので会いに来ました』」と言いました。『本当にやったんですか?』と言われました」
課題は継続できるか 連携先を発掘中
ただ、こうした立石さんの発案は、継続性を考えると課題がある。現在、製薬メーカーや職能団体、業界団体に「一緒にできないか?」と話をするなど、連携先を発掘中だ。
コメント
素晴らしい取り組みです。
ポスター1枚ですが、本当に困っている・苦しんでいる人の目には留まるはずです。
そこから何かが変われるかもしれません。
本当に素晴らしい活動ですね。立石さんの気づきと行動力、そして社長さんの後押しの言葉、すべてに感動しました。
苦しんでいる人たちに必要なのは、適切な相談先と相談してもいいという風潮だと思います。
立石さんの活動、応援しています!
良い考え方ですね。
店内の掲示ポスターを観る子供達が確実に見るのは商品の横でしょう。それを探しに来ているのだから
孤独を感じている子は多いですよ
だから同じような人が集まる場所に集まる
以前はそれでも個々で落とし処を見つけて卒業(大抵パートナーを見つけて)出来ました。
孤独でなければ回避は可能
必ずではありませんが多数拾える命もあるでしょう。
ただ依存症はそんなに甘いものでもない。
希死念慮は消えることがない
ODを辞められたとしても
それは続きます
結果希死念慮が怖いからODをするようになる人も一定数居ます。
結果今回の法改正で自殺者は増えるでしょう。
国は法を変えて迄守ったのは既得権益者だけです。ODする側を守ったのではなく切り捨てたと考える人しか居ないのだから。
涙が出た
ポスター1枚に救われる人がきっといる!
社長の言葉も素晴らしい
私に何ができるだろうか
私はこれからツルハドラックで買い物をします
素晴らしい取り組みだと思います。薬剤師として私も ODの事は勉強していますが、孤独や生きづらさから ODしてしまうの子供たちに、なんでも話せる居場所が必要ですよね。
立石さんがひとりのアルコール依存症者との出会いから、助けるってなんだろ?その感覚こそが素晴らしいと思います。若者のODも薬を売るのを断るだけではなく、孤立し苦しんでいる人を助けたいと発案し、社会に一石を投じた行動に深く感動しました。
感動して胸が震えました。
思いついたことを行動に移す、松本先生にも会いに行くって凄いですね。それと努力。本当に頭が下がります。
救われる人が必ずいると思います。
この記事が多くの人に広まりますように!!
若年層のOD(過量服薬)問題が深刻化する中、ツルハドラッグが支援につながるポスターを店内に掲示した取り組みは、社会に大きな示唆を与えています。
「誰かのSOSを見逃さない」――その姿勢に深い感銘を受けました。
アディクションに苦しむ人たちに私たちができることを、一人ひとりが考え、行動へとつなげていく。
その輪が広がることを心から願います。
若年層のOD(過量服薬)問題が深刻化する中、ツルハドラッグが支援につながるポスターを店内に掲示した取り組みは、社会に大きな示唆を与えています。
「誰かのSOSを見逃さない」――その姿勢に深い感銘を受けました。
アディクションに苦しむ人たちに私たちができることを、一人ひとりが考え、行動へとつなげていく。
その輪が広がることを心から願います。
すばらしい取り組みですね。
立石さんもすごいが、『競合がやっているからとか、宣伝になるからとかじゃなく、誰もやっていないことだし、いいことなんだから胸を張ってやったらいい』という社長の言葉に感動しました。リーダーはこうあってほしい!
すばらしい取り組みだと思いました。これが立石さん個人の経験、想いに端を発したプロジェクトということにさらに感銘を受けました。問題意識を持った人が誰か一人でも声をあげ、働きかけていくことで実現する支援。声をあげよう、と改めて思わせていただきました。
私から始まりますように!と様々な活動に取り組んでいますが、この方の活動もまさに!1人が当事者意識を持ち、取り組み始めたことが、全国に広がろうとしている。どんなことも他人事ではなく当事者意識を持って取り組めば、社会は変わり、やがて自分を守る仕組みが社会に構築されていく!と確信を深めるエピソードを知ることが出来て嬉しく思います。これからの展開も発信して下さい。どうか若い人達の多くの生命が守られますように!
「そういうことこそ、もっと胸を張ってやるべきだ」、そんな風に背中を押してくれる社長がいる企業、かっこいい。
立石さんの、解決のために行動できる力も見習いたいです。
しわよせを受けても簡単には声をあげられない子どもたち。大人はそこに甘えてはいけませんね。
