薬物報道の学会報告のために海外へ…飛行機恐怖症を克服して
薬物政策に関する研究調査や国際学会での報告をするために、超えなければならなかったことーー。
それは「飛行機に乗る」ことだった。

公開日:2025/03/12 22:00
筆者は、国際学会での報告や研究調査などのために海外に渡航することがある。
「海外に行けて、いいですね」。しばしば、このように言われる。しかし、筆者にとって、飛行機に乗ることは容易ではなく、高いハードルを超えなければならなかった。
海外での体験もおりまぜながら、2度のヨーロッパ渡航を振り返る。
(ライター・吉田緑)
初ヨーロッパは、イタリアでの学会報告
筆者が初めてヨーロッパを訪れたのは、2023年のことだ。イタリア・フィレンツェで開催された第23回ヨーロッパ犯罪学会(EUROCRIM 2023)に参加し、日本の薬物報道の現状について報告した。

報告を終えてオーディエンスと会話した際に、日本の謝罪会見について不思議がる人もいた。「謝罪」にどのような意味があるのかは、筆者の関心ごとのひとつである。
当時の日本では、大麻の使用を犯罪化するための議論が進んでいた。しかし、イタリアでは、嗜好目的での大麻の自己使用や所持は、非刑罰化されている(所持量などの制限はある)。街をぶらりと歩いていると「大麻ショップ」もみられた。

販売されていたのは、CBD(カンナビジオール)製品だ。CBDは大麻の成分のひとつで、依存性や乱用性がないとされている。「CANNAAQUA」と書かれたCBDウォーターもあった。

筆者は、異国の地を歩くことよりも、飛行機に乗ることに恐怖心があった。行きの飛行機では、目的地に無事に到着したものの、同行者の荷物が忽然と消えた。ロストバゲージだ。「みんな、生きて到着できて、よかった」と胸を撫でおろしながら、荷物をともに探した。
帰りの飛行機でも、無事に乗り込み、ホッとしたのも束の間、一向に飛ばない。結果的に降ろされ、なんのアナウンスもないまま、ひたすら待つことになった。

乗客たちも、説明がないことに次第にイラつき始める。飛ばない事情を聞くと「天候のため」だという。では、なぜ、ほかの飛行機は飛んでいるのかーー。その問いへの回答はなく、帰国予定の乗り継ぎ便が去ったタイミングで、ようやく飛ぶことになった。
予定では1回の乗り継ぎが3回となり、飛行機への恐怖心よりも帰国できるのかの心配が増した。機内食を食べる機会を逃したため、ポーランドのワルシャワ・ショパン空港で、タリアテッレを食べた。タリアテッレ代は、後日、航空会社に請求した。

2度目のヨーロッパ渡航
2024年9月、第24回ヨーロッパ犯罪学会(EUROCRIM 2024)に参加するため、開催地のルーマニアに向かった。会場は、首都・ブカレストにあるブカレスト大学だった。

筆者は、大麻に関する1990年代からこれまでの報道と、犯罪が構築されていく過程に関する報告をおこなった。
国際学会で報告するたびに、世界的にみて、犯罪が少ないとされる日本だからこそみられる事象の数々があることに気づかされる。薬物報道も、そのひとつかもしれない。諸外国では違法薬物の自己使用以外に、メディアに注目される犯罪が複数ある。
国際学会では、報告者が現れなかったり、場合によってはセッション自体が流れたりすることもある。報告日にはメディアと犯罪に関する4人の報告がおこなわれる予定だったが、報告時間の約30分前に、筆者を含めて2人に減った旨の通知があった。
奇しくも、もう1人の報告者も薬物とメディアに関する研究をしているイギリスの博士課程に在籍する大学院生だった。オンライン空間における若者への違法薬物の販売や広告、若者を守るための対処方法について研究しているという。主に、動画や画像などを投稿するアプリなどで、違法薬物を宣伝する内容がみられる傾向にあるとのことだった。

ルーマニアは、イタリアとは異なり、嗜好用大麻の自己使用や所持は非刑罰化されてはいない。CBDコーヒーなどを販売するショップはあったが、日本でもみられる光景だ。

あるミニスーパーでは、ヘンプシードバーが売られていた。チョコレート味だ。

ルーマニアの名物のひとつに、チョコレートがある。筆者も土産用に、スーパーに買いに出かけた。
アメリカで暮らしたこともある筆者は、日本帰国後、レジで「〇円1点…」などと言いながら、ひとつひとつの商品をきれいにカゴに入れていく店員の対応に感動した。
チョコレートを爆買いしたルーマニアのあるスーパーでも、アメリカと似た光景がみられた。店員は、不機嫌な面持ちで商品を投げ捨てるかのようにカゴに入れていった。

別のスーパーでは、中に入ろうとしたところ「閉店だから」と言われた。「まだ閉店時間ではないのでは」と聞くと「だから、今日はもう閉店したんだよ」と怒り気味に言われた。掲げられている閉店時間よりもはるかに早い時間だった。日本人は、働きすぎかもしれない。
帰国時は、ドイツのフランクフルト空港を経由した。ドイツでは、嗜好用目的での大麻の自己使用や所持などが合法化されている(ただし、年齢や所持量などに制限がある)。可能であれば、街をぶらりと歩いてみたいと思っていた。

しかし、結局仕事に追われ、空港でひたすらパソコンに向かっていた。もはや、飛行機に乗ること自体はこわくなくなっていた。
「飛行機恐怖症」との闘い
筆者にとって、海外に行くことは、夢のまた夢だった。周囲にすすめられ、留学を検討した時期もあったが、事情で見送らざるを得なくなり、悔しさで朝まで泣いたこともある。
しかし、たとえ留学が実現していたとしても、超えなければならない壁があった。それは「飛行機に乗る」というミッションをこなすことだ。
筆者は、幼少期から小学2年生までアメリカ・ニューヨーク州で過ごした。1980年代後半から1990年代初頭のことである。就学前は、日本の保育園・幼稚園にあたるナーサリー(Nursery)とキンダーガーテン(Kindergarten)、小学校は公立の現地校に通った。いずれも共通言語は英語であり、日本人はいなかった。
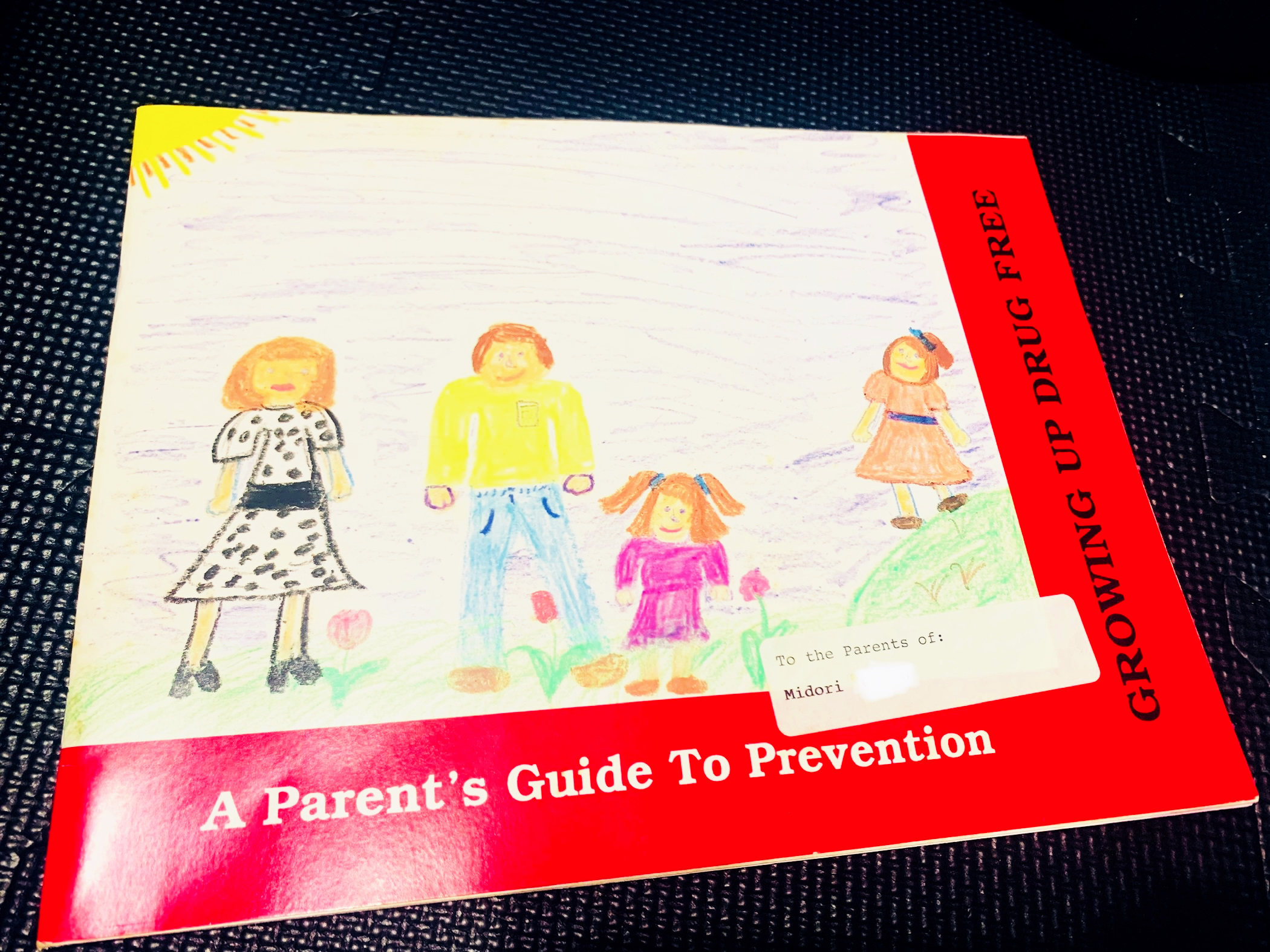
向かいの家には、精神科医の父親と弁護士の母親をもつ3人のユダヤ系の子どもたちが住んでいた。毎日のように遊びに行き、一家のことは、第二の家族だと思っていた。日本への帰国が決まったとき「いつでも帰っておいで。ここはあなたの故郷だ」と言われた。
帰国先の小学校に帰国子女はおらず、「異端」な人間として扱われた。教員とも日本語でコミュニケーションが取れず、周囲が自分に投げかけることばが「悪口」だと気づくことにも時間を要した。
逸脱に関する研究をしているのは、日本帰国後の経験による影響がある。逸脱を生み出すものに興味がある。依存症であっても、違法薬物を使ったとしても、そうでなくても、すべての人は等しく「人」だ。異端視することを疑問に思う。
子ども時代の筆者は「異端視される自分が悪い」と思っていた。「いじめられるほうが悪い」と考えられていた時代だった。コミュニティに適応して溶け込もうと、必死だった。国語辞典や百科辞典などを含めて図書館の本を端から端まですべて読み、日本語を学んだ。
しかし、言語が通じるようになっても、日本に馴染むことはできなかった。
放課後はほぼ毎日、英会話教室に通った。個別指導のほか、週数回はビジネス英語を学ぶ大人たちとともに過ごした。
いつか、故郷であるアメリカに帰るーー。それが、目標だった。しかし、向かいの家に住んでいた第二の家族との文通やメールが、ある日から途絶えるようになった。
そして、2001年9月11日、テレビを見て唖然とした。世界貿易センタービル(ワールドトレードセンター)に飛行機が衝突した。
向かいの家に住んでいた家族にメールを送ると、数カ月してから返事があった。9.11を理由にほとんどの友人たちがニューヨークを離れたこと、それ以前に、別の飛行機墜落事故で一家の父親が亡くなっていたことを知った。
飛行機に恐怖心を抱くようになったのは、故郷と第二の家族のひとりを失ったショックからだ。飛行機が視界に入るだけで吐き気がした。一度だけ海外に行こうとした際には、飛行機に搭乗しようとしたとたんに体調が悪化し、絶望に駆られた。
恐怖症を克服したのは、2022年に薬物政策の調査研究のためにタイに飛んだことがきっかけだ。
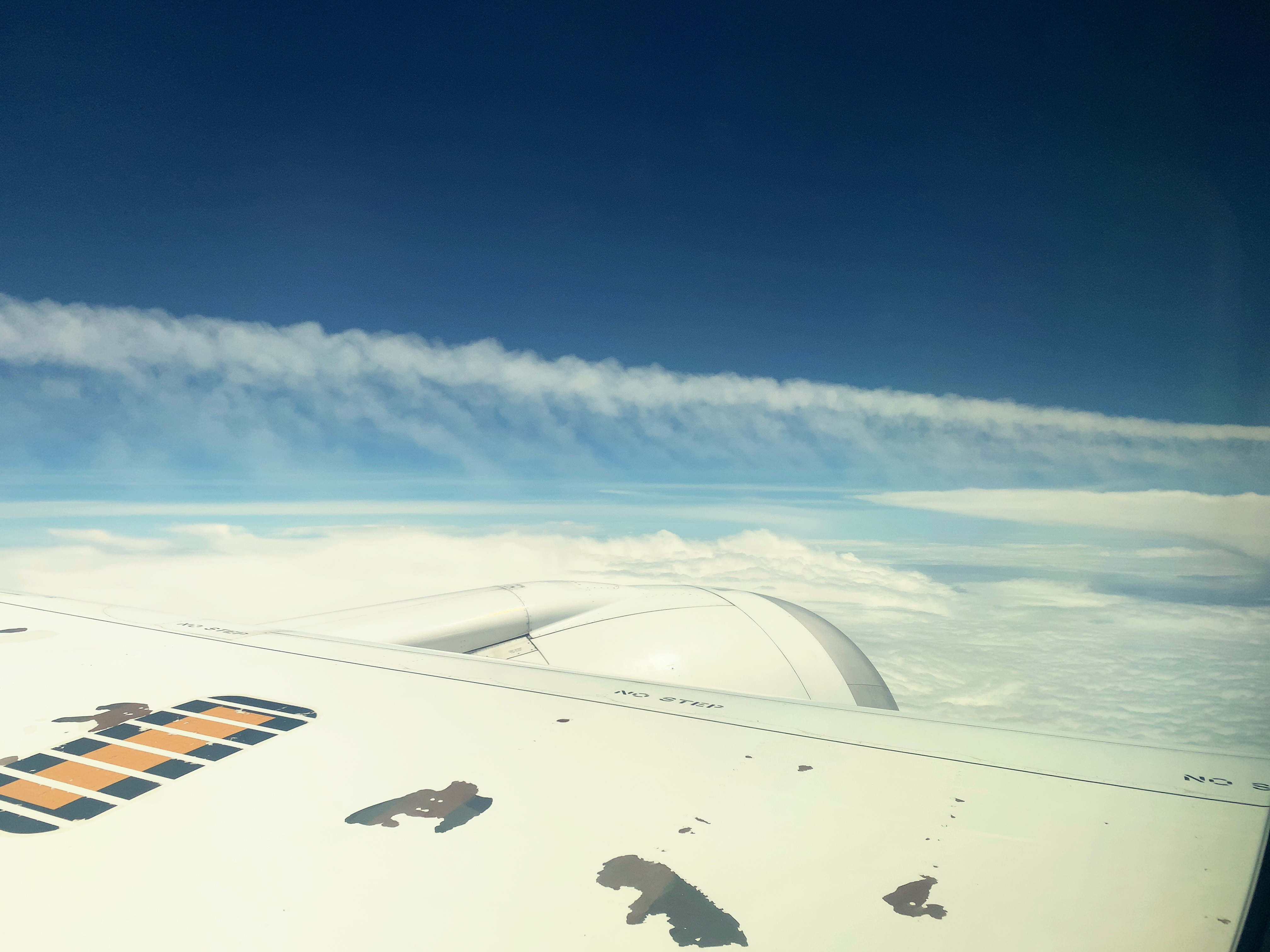
研究できる喜びや知的好奇心が勝った。2023年に再びタイに行き、海外に渡航する体験を積み重ねるうちに、いつの間にか克服していた。
今後も、海外で得た知見を活かして、できることをしていきたい。そして、いつか、第二の家族に会いに行く。
